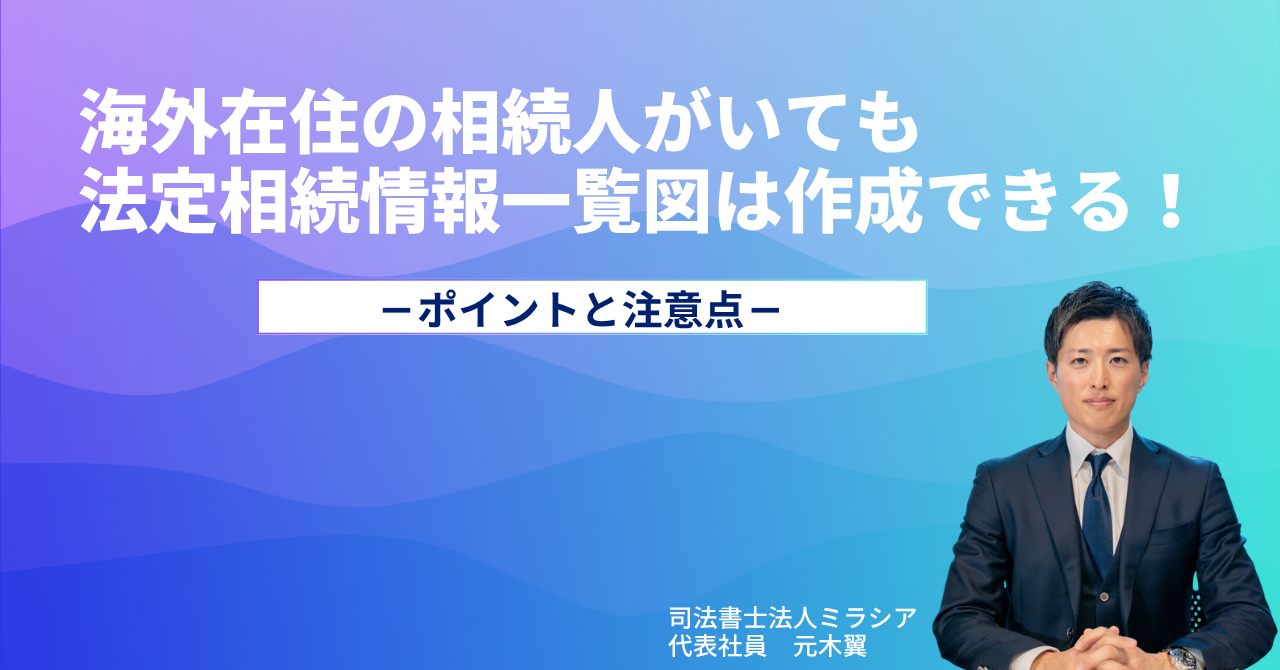
目次
はじめに
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と法定相続人との関係を一目でわかるよう一覧にまとめ、法務局がその内容を公的に認証する書類です。相続手続きの際に必要となる大量の戸籍謄本一式を、この1枚の一覧図の写しで代替できるため、手続きの効率が大幅に向上します。銀行口座の名義変更や不動産の相続登記など、各種相続手続きを進めるうえで非常に便利な制度です。
では、相続人の中に海外在住の方がいる場合でも、この法定相続情報一覧図を作成できるのでしょうか?これは実務でもよくご相談いただくテーマです。
結論からお伝えすると、相続人が海外に住んでいても、日本国籍を保持していれば一覧図の作成は可能です。ただし、海外在住の相続人が含まれる場合には、必要な書類や注意点が日本国内だけのケースとは異なり、少し手続きが複雑になります。
本コラムでは、海外在住者を含む相続において法定相続情報一覧図をスムーズに作成するためのポイントを、相続・認知症対策を専門とする司法書士が、やさしく・詳しく解説します。必要書類の種類や取得方法、住所を記載するメリット、実際の事例紹介、そしてオンラインで完結する方法まで、網羅的に解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、2024年4月1日から相続登記(不動産名義の変更)は法律上の義務となっており、相続が開始してから3年以内に登記申請をしないと**過料(罰金)**の対象になる可能性があります。とくに海外在住の相続人が関与する場合、国際郵送や領事館での証明書取得に時間がかかるため、対応には余裕をもつことが大切です。
早めの準備と専門家への相談が、将来的なトラブル回避につながります。
1. 法定相続情報一覧図とは?
1-1. 法定相続情報一覧図の意義
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍と、すべての法定相続人の戸籍をもとに、誰が相続人であるかを一覧形式で整理した書類のことです。
相続人が複数いる場合でも、相続関係を一目で確認できるように構成されており、法務局がその内容を審査・認証し、「写し(証明書)」として交付してくれます。
この法定相続情報一覧図の大きなメリットは、戸籍一式の代わりとして相続手続きに使える点です。これまでは、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記を行うたびに、戸籍謄本を何通も集めて各機関に提出しなければなりませんでした。しかし、一覧図を作成すれば、1回の戸籍収集で済み、以降の手続きではこの1枚を複数の機関に使い回せるため、非常に効率的です。
この制度は平成29年(2017年)から始まり、現在では相続手続きにおいて広く利用されるようになりました。とくに下記のようなケースでは、法定相続情報一覧図を作成することで手続きの手間と時間を大きく削減できます。
1-2. 法定相続情報一覧図を使うメリット
戸籍を毎回提出する必要がなくなる
→ 各種相続手続き(預貯金の解約、不動産登記、証券口座の名義変更など)が簡略化されます。複数の相続手続きを同時に進めやすくなる
→ 一覧図の写しは何枚でも取得できるため、並行して金融機関や法務局に提出可能です。戸籍の収集が1回で済む
→ 特に被相続人の戸籍が多く、相続人が複数の地域に分散している場合に効果大です。不備や手戻りのリスクを減らせる
→ 法務局の認証を受けた一覧図であれば、相続関係の証明として高い信頼性があります。
このように、相続手続きをスムーズに進めたい方にとって、法定相続情報一覧図は非常に有用な制度です。
戸籍の束を何度も提出することに疲れている方や、相続手続きを一気に進めたいという方は、ぜひ活用をご検討ください。
2. 海外在住でも法定相続情報一覧図は作成できるのか?
2-1. 結論:日本国籍の相続人であれば海外在住でも作成可能
法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の戸籍に基づき、相続関係を一覧表として法務局が認証する制度です。
このため、相続人が海外に住んでいたとしても、日本の戸籍に記載されていれば問題なく一覧図を作成できます。たとえば、国際結婚などで配偶者が海外で生活している場合でも、その方が日本国籍を保持している限り、戸籍をたどって一覧図を作成することが可能です。
2-2. 外国籍の相続人がいる場合は注意が必要
一方で、相続人の中に日本国籍を喪失した方(帰化して外国籍となった方)が含まれている場合は、法定相続情報一覧図を作成できない可能性があります。
この制度では、相続人全員の戸籍謄本が必要ですが、外国籍となった方については日本の戸籍がすでに除籍・閉鎖されており、必要な書類が揃えられないケースが多いからです。
たとえば、以下のようなケースでは一覧図の作成ができない場合があります:
相続人のお子さんが外国籍に帰化している
国際結婚した外国籍の配偶者が法定相続人である
相続人のうち一部が日本の戸籍に記載されていない
このように、戸籍で相続関係を証明できない相続人がいる場合は、一覧図の作成が不可となり、従来通りの相続手続き(戸籍一式や外国の公的書類による証明)が必要となります。
専門家のワンポイントアドバイス
法定相続情報一覧図は、相続人全員が日本国籍であることが前提の制度です。
ご家族の中にすでに帰化された方や外国籍の相続人がいる場合は、一覧図を使わない形での相続手続きを検討しましょう。
一覧図が作成できない場合でも、相続手続きを進められないわけではありません。
この場合は、戸籍謄本一式や外国公的書類(出生証明書・婚姻証明書など)を個別に提出して相続関係を証明する必要があります。
また、相続人の協力が得られない・所在が不明といった事情がある場合は、不在者財産管理人の選任申立てや、法定相続分による単独相続登記などの方法をとることも検討されます。
状況に応じた最適な進め方を判断するには、相続の専門家に早めにご相談いただくのが安心です。
3. 一覧図に相続人の住所を記載すべき理由とは?
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載する欄があります。住所の記載は法的には任意とされていますが、実務上は住所を記載して作成することを強く推奨されます。
その理由は、住所を記載していない一覧図では、銀行や証券会社、不動産登記などの各種相続手続きにおいて、相続人全員分の住民票や住所証明書の提出をその都度求められるケースが非常に多いからです。
実際に、住所を記載せずに作成した一覧図で手続きを進めたものの、金融機関から「住民票の追加提出」を求められる場面が何度も発生し、結果的に住所を追記する形で作り直したというケースも少なくありません。最初から相続人全員の住所を記載しておけば、こうした二度手間を防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。
さらに、2024年4月から施行された相続登記の申請義務化により、不動産を相続した方は原則として名義変更登記を行う必要があります。登記申請には相続人の住民票などの住所証明書類が必要になりますが、住所入りの法定相続情報一覧図を添付することで、その代用として認められるので、提出書類の省略が可能となり得ます。
このように、一覧図に住所を記載することで、相続手続き全体の効率化・迅速化が図れるというメリットがあります。
4. 相続人の住所を記載することによる3つのメリット
住所入りの法定相続情報一覧図を作成すると、相続手続き全般がスムーズに進む場面が多くなります。以下にその主な3つのメリットを紹介します。
メリット1 金融機関での手続きがスムーズに進む
銀行や証券会社の中には、提出された一覧図に相続人の住所が記載されていることを条件にしているところもあります。住所が記載されていない一覧図を提出すると、「相続人全員分の住民票を追加で出してください」と求められることがあり、思わぬ時間と手間がかかります。
最初から住所入りの一覧図を提出していれば、追加書類の提出を求められることなく、手続きがスムーズに完了するケースが多くなるのです。
メリット2 書類不備による差し戻しを防げる
相続手続きでは、遺産分割協議書や委任状など、複数の書類に相続人の住所を記載する必要があります。法定相続情報一覧図にも住所が記載されていれば、他の書類との整合性が取れ、チェックもスムーズになります。
逆に、一覧図に住所がない場合、他の書類と記載内容が不一致と判断されて差し戻しとなるリスクがあります。一覧図に住所を記載することで、書類不備による手続きの遅延ややり直しを未然に防ぐことができます。
メリット3 複数の相続手続きを同時並行で進めやすい
住所入りの一覧図の写しは、希望すれば何通でも取得でき、後日追加で請求することも可能です。
例えば、相続登記と銀行預金の解約手続きを同時に進めたい場合、住所入りの一覧図を複数枚取得して、それぞれの提出先に提出すれば良いのです。これにより、相続手続きを一括で並行処理することができ、全体の処理期間を大幅に短縮できます。
特に相続人に海外在住者が含まれている場合、日本国内にいる相続人とのやり取りや郵送に時間がかかることが多いため、一覧図の効率的活用は非常に有効な対策となります。
相続手続きの早期完了を目指すなら、「一覧図に住所を入れる=手続き効率を大きく向上させる」と覚えておくとよいでしょう。
5. 住所を記載する場合の必要書類(日本在住 vs 海外在住)
法定相続情報一覧図は、相続手続きを効率的に進めるために非常に有効な制度です。その中でも、相続人の住所を記載するか否かは、今後の各種相続手続きのスムーズさを左右する重要なポイントになります。住所の記載は法的には任意ですが、実務上は記載を強く推奨します。ここでは、住所を記載するために必要となる書類を「日本在住」と「海外在住」のケースに分けて詳しく解説します。
◆ 日本在住の相続人:住民票または戸籍の附票を提出
日本国内に住んでいる相続人については、住民票(マイナンバー記載省略)を提出します。また、住民票の代わりに戸籍の附票を使用することも可能です(附票には住所の履歴が記載されており、住所証明書として利用できます)。
取得先:市区町村役場、コンビニ(マイナンバーカードがあれば対応自治体で可)
注意点:
住民票コードやマイナンバーは不要(省略されたものを使用)
相続人個人のものを用意(世帯全員ではなく)
戸籍の附票を使う場合は、相続開始時点の住所が含まれているかを確認
◆ 海外在住の相続人(日本国籍):在留証明書を提出
海外に住んでいる相続人で日本国籍を保持している場合には、**在外公館(日本大使館・総領事館)で発行される「在留証明書」を提出することで住所を記載できます。在留証明書とは、海外に居住する日本人が現住所を証明するための公的な証明書です。
在留証明書の取得手続き:
申請書の準備:各公館の窓口で受け取るか、ウェブサイトからダウンロード。
日本国パスポートの提示:有効なものを持参(原本またはコピー)。持っていない場合は戸籍謄本等で確認されることもあります。
現住所が記載された書類の提出:以下のいずれかの書類が一般的に認められます。
公共料金の請求書(氏名・住所・日付の記載あり)
銀行口座の明細書
運転免許証
賃貸契約書
現地の住民登録証明
申請方法と受領:
原則は本人が窓口で申請
一部公館では郵送申請も可能
即日〜数日で発行(郵送の場合は1週間以上かかることも)
手数料の支払い:
数百円〜1,000円程度(現地通貨)
支払い方法は公館によって異なるため事前確認が必要
注意点:
在留証明書は日本国籍の方のみ発行可能。
外国籍の相続人(帰化者や外国籍配偶者など)には発行されないため、住所を一覧図に記載することはできません。
外国の公証人が作成する宣誓供述書(Affidavit)などは、日本の法務局では住所証明として認められないとされています。
◆ 相続人の住所記載に関するまとめ
| 居住地 | 証明書類 | 発行機関 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本在住 | 住民票 または 戸籍の附票 | 市区町村役場 | 本人分・マイナンバー省略 | 発行後3か月以内のもの/附票は住所履歴要確認 |
| 海外在住(日本国籍) | 在留証明書 | 日本大使館・総領事館 | パスポート・現住所証明 | 郵送申請可能な場合もあり |
| 海外在住(外国籍) | 記載不可 | ― | ― | 外国書類+翻訳で個別対応 |
◆ 在留証明書は相続以外にも活用されます
在留証明書は、相続手続きのほか、以下のような場面でも使われることがあります:
日本の年金受給手続き
在外選挙の登録
日本国内の受験・進学手続き
特に長期間海外に居住している方は、在外公館との連絡体制を整えておくことで、万一のときに迅速な対応が可能になります。
◆ 専門家からのアドバイス
在留証明書は海外での取得・郵送に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
相続人が複数名海外在住の場合は、全員分の在留証明書が必要になります。
外国籍の相続人が含まれる場合は、一覧図を利用しない前提で、個別手続きの流れを早期に設計することが重要です。
6. 委任状や署名証明書が必要になるケース
海外在住の相続人がいる場合、相続手続きを円滑に進めるためには、誰が手続きの主導者(申出人)となるかを事前に決めておくことが大切です。
法定相続情報一覧図の申出(申請)は、原則として相続人のうちの1名が行います。相続人全員が海外在住である場合や、日本に住む相続人が高齢や体調不良などで動けない場合には、司法書士や税理士などの資格者に代理申請を依頼することも可能です。一定の資格を有する専門家であれば、代理人として一覧図の交付申請が認められており、戸籍収集から一覧図の取得まで一括で依頼することができます。
6-1. 遺産分割協議は全員参加+印鑑証明書が必要
相続手続きの中でも、銀行での預貯金払戻し手続きや、不動産の名義変更登記(相続登記)は、原則として相続人全員での遺産分割協議を前提とした手続きになります。
このとき、遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印押印および印鑑証明書の添付が必要です。ところが、相続人の一部が海外在住で一時帰国できない場合、遺産分割協議書や委任状の作成にあたって、署名の真正性を証明する追加書類が必要となります。
6-2. 海外在住の相続人が用意すべき「署名証明書(サイン証明)」とは?
署名証明書(サイン証明)とは、日本で言う「印鑑証明書」の代わりとなる書類です。日本の印鑑登録をしていない海外在住者が、遺産分割協議書や委任状に実印の代わりとして署名する場合に、その署名が本人によるものであることを在外公館(日本大使館や総領事館)が証明するものです。
【取得の流れ】
在外公館の窓口で申請(※代理人申請不可)
署名証明が必要な書類(未署名の状態)を持参
領事の目前で本人が署名を行い、その場で認証を受ける
領事が認証を記した署名証明書を発行
この署名証明書を遺産分割協議書や委任状に添付すれば、日本国内における実印+印鑑証明書と同等の効力が認められ、各種相続手続きに使用できます
6-3. 郵送による署名証明書の活用と手続きの流れ
署名証明書付きの遺産分割協議書や委任状を取得したら、それらの書類を日本国内の相続人または手続きを担当する司法書士に郵送します。
受領後は、日本にいる相続人や代理人が、遺産分割協議書の残りの署名押印を行い、相続登記や金融機関手続きを進めることができます
6-4. 署名証明が取得できない場合の代替手段
どうしても在外公館に出向くことが難しい場合は、以下のような代替手段をとることも可能です:
居住国のNotary Public(公証人)による署名証明書を取得
日本への一時帰国時に、日本の公証役場で認証を受ける
ただし、
日本語訳の添付
ハーグ条約加盟国の場合は Apostille(アポスティーユ)認証
非加盟国の場合は在外公館による領事認証
といった追加手続きが必要になる場合があるため、事前に日本側の登記所や金融機関に確認しておくことが重要です。
7. 【事例】海外在住の相続人がいる相続手続きの実例
最後に、実際に海外在住者を含む相続手続きを行ったケースを紹介します。具体的な流れや注意点をイメージする参考になればと思います。
〈事例:アメリカ在住の長男Aさんが日本の実家の相続手続きを行ったケース〉
被相続人である父親が東京で他界し、相続人は長男のAさん(アメリカ在住)と長女Bさん(日本在住)の2名でした。Aさんは日本には長年帰国しておらず、「自分が海外在住でも法定相続情報一覧図を作って手続きを進められるのか」と不安を抱えて専門家に相談しました。
まず弊社で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、長女Bさんの戸籍・住民票を迅速に収集しました。次に、Aさんには在ニューヨーク日本総領事館で在留証明書を取得していただき、併せて預貯金解約手続き等に備えて署名証明書も取得してもらいました。幸いAさんは総領事館まで車で1時間ほどの場所に居住しており、領事館の予約もスムーズに取れたため、1週間ほどで必要書類を入手できました。
取得した戸籍謄本類と在留証明書を用いて法務局に法定相続情報一覧図の交付申請を行ったところ、相続人2名(うち1名は海外住所)の住所が記載された一覧図の写しが無事に交付されました。その後の銀行手続きでは、この一覧図の写しと署名証明書付きの委任状を提出することで、Aさん自身が来日しなくても預金の解約払戻しが完了しました。また、不動産(実家の土地建物)の相続登記についても、AさんBさん双方が署名・押印した遺産分割協議書と一覧図を用いて申請し、オンラインで登記完了通知を受領しています。
このケースでは、戸籍収集からすべての相続手続き完了まで約2ヶ月半かかりました。海外との郵送に要する日数や領事館での証明取得の手間はあったものの、結果的にAさんは一度も日本に帰国することなく相続手続きを終えることができました。 専門家の適切なサポートのもと、テレビ電話やメールで緊密に連絡を取りながら進めたことで、Aさんの不安も解消され「オンラインでここまで完結できるとは思わなかった、非常に助かった」との声をいただきました。
海外在住の相続人がいる場合でも、法定相続情報一覧図を活用することで戸籍集めは1回で済み、遠隔地からでも効率よく手続きを進められるということがこの事例から分かります。大切なのは早めの準備と専門家への相談です。郵送や証明書取得に時間がかかる分、国内相続より計画的に進めましょう。
まとめ
相続人の中に海外在住者がいる場合でも、日本国籍を有していれば一覧図の作成は可能です。必要な戸籍謄本を揃えれば、海外からでも申請できます。一覧図への住所記載は任意ですが、実務上は記載を強く推奨されます。記載がないと、手続きごとに住民票や在留証明書を個別に提出する必要があり、非効率です。
◆ 住所を記載するための書類
日本在住の相続人:住民票または戸籍の附票
海外在住の相続人(日本国籍):在外公館が発行する在留証明書
在留証明書は日本大使館・領事館で取得でき、現住所を示す書類(公共料金請求書など)を提示して申請します。
◆ 本人が来日できない場合の対応
相続手続きで来日が難しい場合は、委任状+署名証明書を用意すれば代理人による手続きが可能です。署名証明書は在外公館で署名を認証してもらう書類で、印鑑証明書の代替として使われます。
◆ 外国籍の相続人がいる場合
外国籍の相続人は日本の戸籍に記録がないため、一覧図の作成は不可です。相続関係を証明するには、出生証明書や婚姻証明書などを個別に用意する必要があります。海外在住の相続人が関わる相続手続きは時間がかかるため、早めの準備がスムーズな対応のカギとなります。
海外在住の相続手続きも専門家にお任せください
司法書士法人ミラシアは相続・認知症対策の専門事務所として、海外在住の相続人がいるケースの相続手続きについて豊富な実績があります。戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、不動産の相続登記、預貯金解約手続きまで一括してサポート可能です。遠方にお住まいの方ともメールやオンライン会議等で密に連絡を取り、ご来所・ご来日いただかなくても手続きを完結することができます。実際に「実績多数」「オンライン完結」を実現してきた当事務所が、お客様の不安を解消し円滑な相続手続きをお手伝いいたします。
海外在住者が含まれる相続でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。専門家の経験に基づくアドバイスとサポートで、大切なご家族の相続手続きを安心して進めていただけるよう全力でサポートいたします。

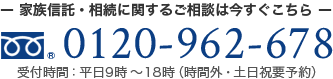
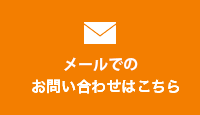
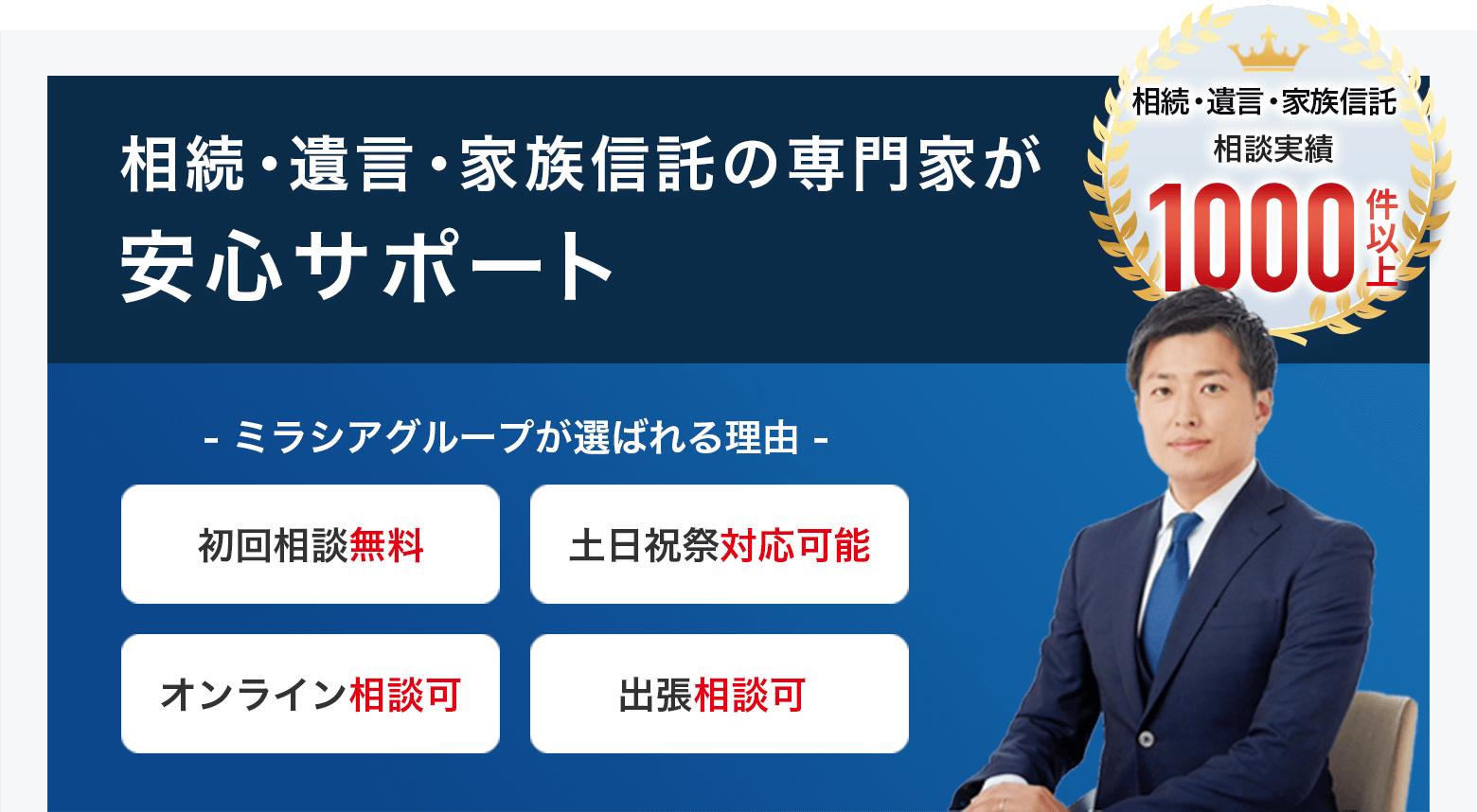
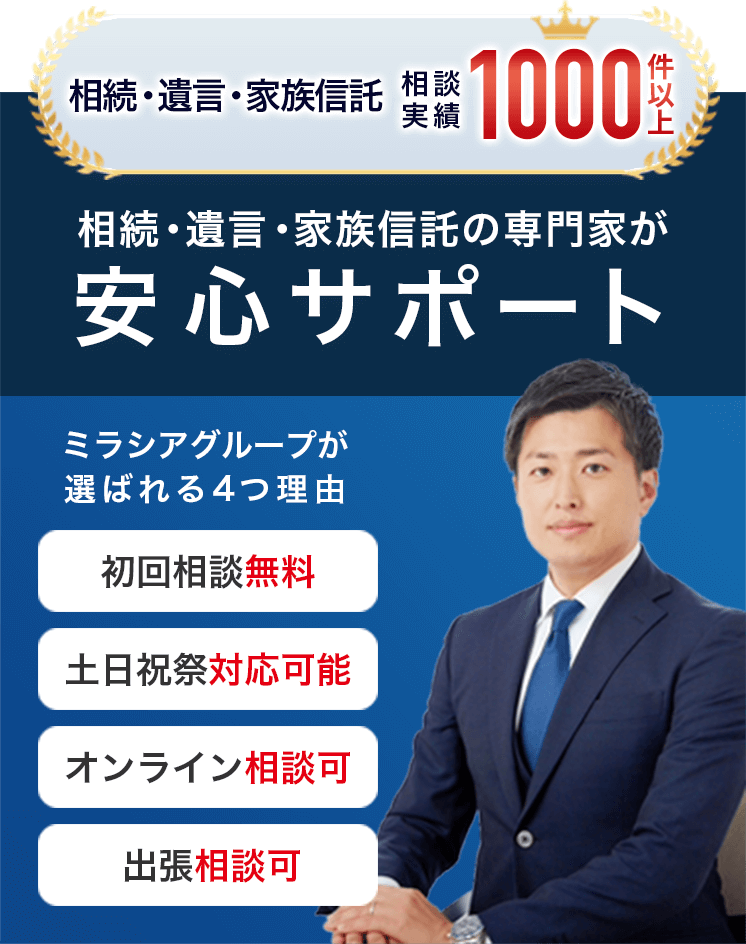


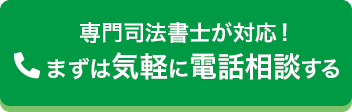
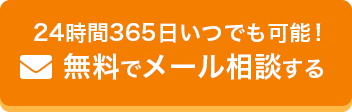
コメント