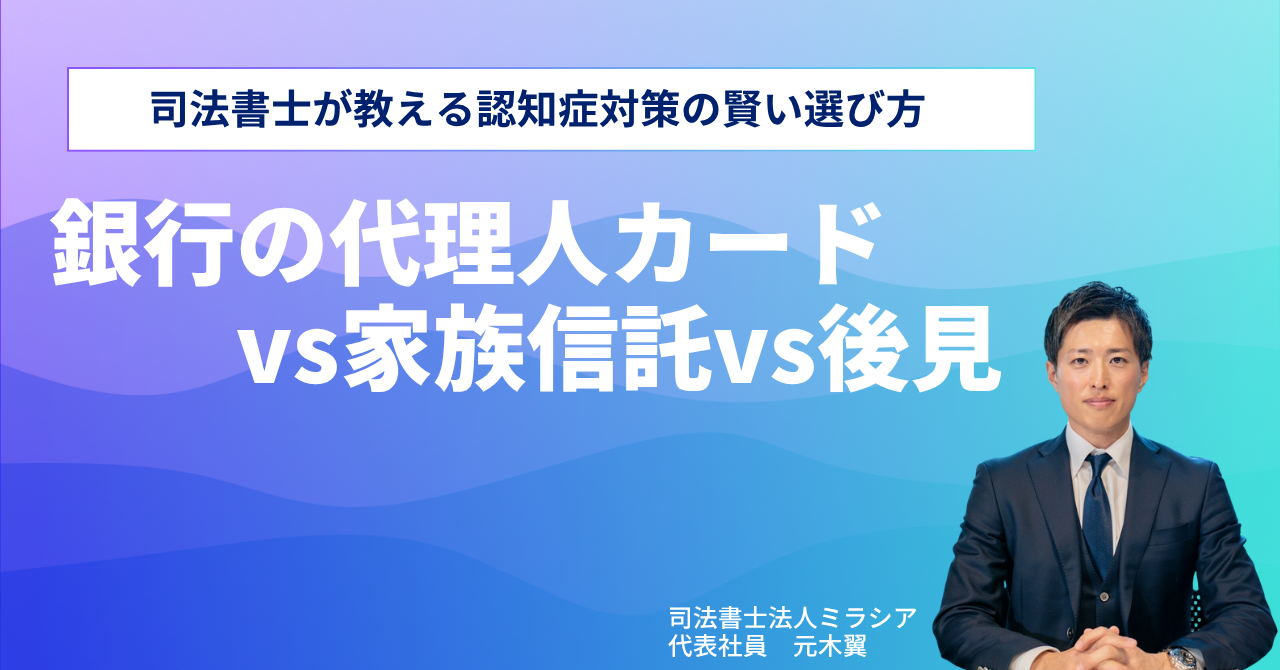
目次
はじめに
「親の代わりにお金をおろしたい」「介護費や医療費を支払いたい」——
そんな時に利用されるのが、銀行の「代理人カード」という制度です。
高齢の親が銀行に行きづらくなったとき、家族が代わってATMで入出金や振込ができるため、日々の資金管理を支える手段として注目されています。
ただし、この制度はあくまで「元気なうちのサポート」に特化したものであり、どんな場面でも対応できるわけではありません。
認知症の症状が見られるようになると、銀行側が本人の意思確認を慎重に行うようになり、場合によっては口座が一時的に凍結されることもあります。また、できることがATM取引に限られていたり、定期預金の解約や名義変更などは行えないなど、制度の限界や制約を知らずに利用すると、思わぬ不都合が生じるケースもあるのです。
本コラムでは、代理人カード制度の基本や利用可能な範囲、さらには家族信託や成年後見制度との違いについて、図解や比較表を交えながら丁寧に解説します。
「親のお金の管理、何から考えればいいのか分からない」——そんな方に向けて、実務に基づいた正確で実践的な情報をお届けします。
1. 代理人カードとは~家族が代わりに取引できる制度~
1-1. 代理人カードとは
代理人カードとは、銀行が口座名義人とは別に発行する専用キャッシュカードです。あらかじめ登録した家族などの代理人が、このカードを使って本人に代わりATMで預金の出し入れや振込を行える仕組みになっています。たとえば親御さんが入院していたり、足腰が弱って銀行まで出向けない場合でも、子どもや配偶者が代理人カードを使えば、現金の引き出し・預け入れ・振込といった日常的な取引をスムーズに代行できます。
銀行窓口やATMでは、原則として「本人以外によるキャッシュカード利用」は禁止されています。仮に家族が本人のカードと暗証番号を預かってATMを操作すると、規定違反となり、発覚した場合口座が凍結される恐れがあります。代理人カードを正式に発行すれば、委任状などを毎回用意しなくても、家族が正規の手続きとして取引できるため安心です。近年のカードにはICチップが搭載され、不正利用を防ぐセキュリティ対策も強化されています。
ただし、代理人カードは万能ではありません。本人が認知症などで判断能力を失った場合、銀行の判断でカード利用が停止されるのが一般的です。つまり、この制度は「本人に判断能力がある間のサポート策」にとどまり、認知症が進行した後の資産凍結リスクまで完全に防げるわけではありません。また、利用できる範囲や条件に制限がある点にも注意が必要です。
以上を踏まえ、実際に代理人カードを申し込む際は「どこまでの取引が可能か」「認知症発症後はどうなるか」を事前に確認し、万が一に備えた別の手段(家族信託や成年後見制度など)も合わせて検討しておくことが大切です。
以下ではまず代理人カードの基本的な仕組みと制限、そして本人が認知症になった場合の口座凍結リスクについて解説します。
1-2. 代理人カードの手続き
この代理人カードを発行するには、まず、必ず口座名義人ご本人が銀行の窓口で申請する必要があります。代理人になるご家族が単独で申し込むことはできず、あくまでご本人の「カードを作りたい」という明確な意思が前提となります。手続きの際は、原則として口座名義人ご本人と代理人になる予定のご家族が一緒に来店し、双方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、通帳、そして届出印を提出して申し込みます。発行できるカードは、1つの口座につき1枚(複数発行できる金融機関もあり)と限られているのが一般的です。
次に、代理人になれる人の範囲にも条件があります。多くの金融機関では「口座名義人と同居し、生計を共にしている成人のご親族」を対象としており、配偶者や同居している18歳以上のお子さまなどが典型例です。友人や知人、別居しているご親戚は基本的に代理人にはなれません。
ただし、銀行によっては条件が異なり、例えば「二親等以内の血族」まで認めている場合もあります。この場合、別居しているお子さまや、お孫さん、ご兄弟姉妹でも代理人に指定できる可能性があります。また、すでに成年後見人が選任されている場合は、その後見人を代理人とすることも可能です。
代理人カードを申し込む際には、一般的に以下のものが必要です。
●通帳またはキャッシュカード(対象となる口座のもの)
●届出印(いわゆる銀行印)
●本人および代理人それぞれの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
発行にかかる手数料は銀行によって異なります。たとえば、みずほ銀行では「みずほマイレージクラブ」の会員であれば無料、それ以外の方は1,100円(税込)が必要です。一方で、三菱UFJ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行などでは、手数料が無料となっているのが一般的です。なお、たとえ有料であっても数百円~1,000円程度が相場のため、費用面が大きなハードルになることは少ないでしょう。手軽に始められる制度として、事前の備えとして導入しておく価値は十分にあります。
代理人カードは、ご本人の意思がはっきりしているうちにしか作ることができません。将来のもしもに備えて、親御さんがお元気なうちに一度ご家族で話し合い、必要であれば早めに発行を検討しておくことをお勧めします。まずは、取引のある金融機関へ相談してみましょう。
1-3. 【図表】代理人カードでできること・できないこと
銀行の代理人カードを発行すると、本人に代わって以下のような預金取引が可能になります。一方で、代理人カードでは対応できない手続きも多くあります。主な「できること」「できないこと」を整理すると次のとおりです。
| 代理人カードでできること | 代理人カードでできないこと |
|---|---|
| ・ATMでの現金の引き出し・預け入れ ・ATMでの振り込み(※上限額あり) ・残高照会・通帳記帳(銀行による) (※一部、代理人カードで窓口払戻し可能な銀行も) | ・キャッシュカード利用限度額の変更 ・定期預金の中途解約 ・投資信託や外貨預金などの売却・解約 ・通帳・カードの再発行手続き ・インターネットバンキングの利用 ・口座名義人の死亡後の出金(相続手続が必要) |
代理人カードでできることには制限があり、その内容や利用上限額は銀行によって異なります。
一般的には、普通預金口座を対象としたATMでの入出金や振り込みが可能な範囲と考えるのがよいでしょう。一方で、以下のような重要性の高い取引や本人確認を要する手続きは、代理人カードでは対応できません。
・定期預金の中途解約
・大きな金額の出金や振込
・住所変更や連絡先変更などの登録情報の変更
・他行宛ての細かな振込依頼、投資商品の新規契約
また、代理人カードでは本人確認ができないため、銀行窓口での詳細な手続きは一切行えないのが通常です。
これらの制限は、たとえ家族であっても、本人の意思に反する不正な操作や資産の不適切な移動が行われることを防ぐ目的で設けられています。利用にあたっては、できること・できないことをしっかり理解したうえで、補完策(家族信託や後見制度など)も含めて検討することが重要です。
1-4. 本人の認知症が進行すると使えなくなるおそれがある
代理人カードは、あくまで本人に判断能力があることが前提の制度です。
たとえば、認知症が進行して銀行側が「本人の意思確認ができない」と判断した場合、口座は凍結され、代理人カードも即時に凍結となる可能性があります。ATMでの引き出しや振込はもちろん、定期預金の解約なども一切できなくなるおそれがあります。
これは、銀行が「本人の財産を守る」という観点から、認知症の兆候が見られた時点で取引を制限する措置を取るためです。たとえ家族であっても、暗証番号を使って無断で引き出すことは、銀行との契約違反にあたり、問題があります。
実際のところ、「親が認知症になっても代理人カードがあれば大丈夫」と誤解されがちですが、これは大きな落とし穴です。代理人カードは“元気なうちだけ”使える制度であり、認知症発症後の口座凍結を防ぐことはできません。
将来の認知症リスクに備えるのであれば、「予約型代理人サービス」や「家族信託」「任意後見制度」など、より継続的な管理が可能な手段を事前に検討しておく必要があります。代理人カードはあくまで一時的・補助的な手段として位置づけ、本格的な認知症対策には別の制度を併用することが重要です。
【参考コラム】
2. 各金融機関の代理人サービス比較(主要銀行・証券の制度一覧)
銀行によって「代理人カード」の名称や利用条件、申し込み方法は異なります。特に三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行などのメガバンクをはじめ、ゆうちょ銀行や信託銀行、証券会社(大和証券など)も独自の代理人サービスを提供しています。
ここでは、主要な金融機関における代理人サービスについて、以下の観点で比較します:
誰が代理人になれるか(対象者)
申し込み方法や必要書類
発行手数料
利用可能な取引内容
主な制限や注意点
オンラインバンキングへの対応の有無 など
ご家庭で利用している金融機関の制度を事前に確認し、どのサービスが使えるのか把握しておくと安心です。
2-1. 主な金融機関における代理人サービス比較(2025年現在)
| 金融機関(サービス名) | 代理人の対象者 | 申込方法・必要書類 | 発行手数料 | 利用できる取引 | 制限・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行(代理人カード) | 同一生計の親族1名(16歳以上も可) | 名義人と代理人が窓口へ来店し、通帳・届出印・本人確認書類を提出 | 無料(条件により1,100円) | ATMでの出入金、振込、残高照会 | 1口座1枚のみ、定期預金や投資商品は不可、オンラインバンキング非対応 ※予約型代理人サービスあり |
| みずほ銀行(代理人カード) | 配偶者または二親等以内の血族、同居親族(成年後見人も可) | 名義人と代理人が窓口へ(代理人の同行は任意)、通帳・届出印・本人確認書類を提出 | 1,100円(マイレージクラブ会員は無料) | ATMでの出入金、振込、残高照会 | 1口座1枚のみ、ATM利用限度額は年齢等で制限あり、オンライン非対応 ※代理人予約サービスあり |
| 三井住友銀行(代理人キャッシュカード) | 同居かつ生計同一の親族(最大2名まで、18歳以上の子も可) | 名義人本人が窓口で申込、通帳・届出印・双方の本人確認書類が必要 | 無料 | ATMでの出入金、振込、残高照会 | 最大2枚まで発行可能、ATM限度額制限あり、通帳・カードの再発行手続き不可、オンライン非対応 |
| ゆうちょ銀行(ゆうちょ代理人カード) | 同一住所の親・配偶者・子など(原則18歳以上) | 名義人と代理人が窓口で申込、通帳・届出印・本人確認書類を提出 | 無料 | ATMでの払戻し、預け入れ、振替など | 総合口座が対象、1口座1枚のみ、ATM利用上限あり、ゆうちょダイレクトは利用不可 |
| 三菱UFJ信託銀行(つかえて安心信託) | ※家族信託型サービスのため、通常の代理人カードとは異なる | 信託口座開設と同時に代理人(受託者)を契約で設定 | 手数料は契約内容に応じて発生 | 預金・有価証券等、信託財産全般の管理が可能 | 信託財産に限るが、他金融機関含め柔軟な管理が可能。成年後見制度不要で継続利用可 |
| 大和証券(予約型代理人サービス) | 配偶者、二親等以内の親族、または同性パートナー1名 | 名義人と代理人が窓口で予約契約を締結(認知機能に問題がない段階で) | 無料 | 判断能力が低下した後、代理人による売却・出金・住所変更等の手続きが可能 | 資産の新規購入は不可、利用には医師の診断書が必要。オンラインは制限あり |
上記は主要金融機関の代表例です。地方銀行や信用金庫でも類似の代理人制度が用意されていることが多いですが、細かな条件や申込手順は各行で異なります。
「予約型代理人サービス」は一部の大手金融機関に限られており、提供の有無は事前確認が必要です。
ご家族の状況や資産管理の方針に応じて、各制度の特徴を理解し、必要に応じて家族信託や任意後見制度と組み合わせた対策を検討すると安心です。
3. 代理人カードのメリットとデメリット
代理人カードは、高齢の親御さんの預金管理を家族がサポートするうえで手軽に導入できる制度です。家庭裁判所の手続きを必要とせず、比較的すぐに利用を開始できる手軽さが魅力ですが、一方で認知症への対応やトラブルリスクといった注意点も存在します。ここでは、司法書士の立場から、代理人カードの主なメリットとデメリットを整理します。
3-1. 代理人カードの主なメリット
① 手続きが簡単で即日発行も可能
銀行窓口で通帳・届出印・本人確認書類を持参して申請するだけで発行でき、特別な公的手続きは不要です。名義人と代理人がそろって来店すれば、その日のうちにカードを受け取れるケースもあります。成年後見制度のように申立てから数ヶ月かかる制度と比べて、急な入院など緊急時にも迅速に対応できる点は大きなメリットです。
② 家族が正規の手続きでATM取引ができる安心感
代理人カードがあれば、親のキャッシュカードをこっそり使う必要がありません。正規の手続きでATM取引ができるため、心理的負担や法的リスクを避けられるのは大きな安心材料です。暗証番号を忘れがちな高齢者の代わりに操作できるという点でも便利です。
③ 預金残高や収支状況を把握しやすい
代理人カードを使えば、通帳記入や残高照会も可能になり、家族が親の資産状況を可視化できるようになります。「毎月どれくらい年金が入っているか」「介護費用がどれくらい出ているか」などを確認できるため、計画的な支出や資金準備にもつながります。これは将来の相続や生前整理にも役立つ要素です。
④ コストが低く導入しやすい
代理人カードの発行手数料は無料〜1,000円程度と低く、維持費もかかりません。成年後見制度では年間数十万円の報酬が発生することもあり、家族信託でも公正証書や登記に費用がかかるため、代理人カードは非常にコストパフォーマンスの高い制度です。まずは「お試しの対策」として導入しやすく、財産管理方法を検討する“つなぎ策”としても有効です。
3-2. 代理人カードの主なデメリットと注意点
① 認知症になると使えなくなる
代理人カードは、名義人に判断能力がある間のみ使用できます。認知症の症状が進んで銀行が「意思確認が困難」と判断した場合、口座は凍結され、カードも利用停止になります。実際に「親が認知症になり代理人カードが使えず困った」という相談は少なくありません。結果として、成年後見制度の申立てが必要になることも多く、認知症対策としては不十分といえます。
② 利用範囲が限定的
代理人カードでできることはATMでの入出金や振込などに限定されます。定期預金の解約や投資信託の売却といった大きな取引は対象外であり、不動産や介護契約など、銀行以外の財産管理には対応できません。さらに、銀行ごと・口座ごとに個別の申請が必要であるため、複数口座を持つ場合にはその都度手続きが発生します。
③ 不正利用や家族間トラブルのリスク
代理人カードは家庭裁判所や専門家などの監督機能がないため、不正利用や資金の使途不明といった問題が起こる可能性があります。特に相続を見据える家庭では、「勝手に使ったのでは」といった疑念が生まれやすく、兄弟姉妹間の不和や相続トラブルに発展するリスクもあります。定期的に出金履歴を共有する、家族会議で透明性を保つなど、信頼を前提とした運用が求められます。
④ 死亡後の使用は禁止、相続の妨げになることも
名義人が亡くなった後も代理人カードを使用すると、相続手続き上の違法行為に該当する恐れがあります。名義人が死亡した時点で口座は凍結され、正式な相続手続きが必要です。うっかり使ってしまった場合でも、法的責任を問われるリスクがあります。
⑤ 家族に資産状況が筒抜けになる
代理人カードを渡した家族は、名義人の預金残高や収支情報をすべて把握できるようになります。「資産を知られたくない」という親の気持ちや、「相続トラブルを避けたい」という子の心理的負担も無視できません。一人の子だけを代理人にすることで、他の兄弟姉妹との間に不公平感が生まれることもあります。
3-3. 専門家の視点:代理人カードだけでは足りない
代理人カードは非常に便利な制度ですが、「これさえあれば万全」というものではありません。特に認知症リスクへの備えとしては限界があるため、将来を見据えて、家族信託や任意後見制度などの制度と併用することが重要です。
「親はまだ元気だけど、念のため準備しておきたい」と思っている段階であれば、代理人カードは手軽に始められる制度として有効です。ただし、使える場面と使えなくなる条件をしっかり理解し、他制度との役割分担を明確にしておくことが、安心できる老後対策につながります。
4. 銀行の「予約型代理人サービス」とは? – 認知症後も使える新制度
これまで一般的だった「代理人カード」は、口座名義人本人に判断能力がある間しか利用できないという大きな制約がありました。この課題に対応するため、近年多くの金融機関が導入を開始したのが「予約型代理人サービス」です。
このサービスは、本人が将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ指定した代理人が銀行取引を継続できるようにする仕組みです。
現在(2025年時点)、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などのメガバンクやりそな銀行、イオン銀行といった多くの金融機関で導入が進んでいます。
4-1. 予約型代理人サービスの仕組み
予約型代理人サービスは、一般的に以下の流れで利用します。
事前の代理人登録 本人(口座名義人)と代理人になる予定の方が一緒に銀行窓口へ行き、「将来、本人の判断能力が低下した際には、登録した代理人が金融取引を行う」という内容の契約を結びます。代理人として登録できるのは、配偶者や二親等以内の親族が基本ですが、金融機関によっては事実婚のパートナーや同性パートナーを対象に含める場合もあります。
判断能力低下時の届出 後日、本人が認知症などによりご自身の意思で取引を行うことが困難になった場合、代理人がその旨を証明する医師の診断書などを銀行に提出します。
代理取引の開始 銀行が提出された書類を確認し、本人の判断能力低下の事実を認めた後、代理人による取引が開始されます。銀行によっては、本人口座のキャッシュカード利用を停止するなどの措置を取ったうえで、代理人専用カードを発行したり、代理人が窓口で手続きを行えるようにしたりします。
この制度を利用することで、認知症発症後も家族が本人の口座から生活費や介護費用などを円滑に引き出せるようになり、生活の継続性を守ることができます。手続きは比較的シンプルで、多くの金融機関では契約時の手数料を無料としており、利用しやすい制度といえるでしょう(ただし、診断書の取得費用は自己負担です)。
4-2. 通常の代理人カードとの違いと注意点
予約型代理人サービスは非常に有用ですが、利用にあたってはいくつかの注意点や限界も理解しておく必要があります。
◎ 取引範囲は銀行内に限られる このサービスで代理人が行えるのは、あくまでその銀行内での取引に限られます。例えば、預金の入出金や定期預金の解約、投資信託の売却などが主な対象です。 不動産の管理や売却、介護施設の入居契約、医療に関する同意など、銀行外の法律行為や契約手続きは一切行えません。あくまで「金融取引に限定された代理制度」と認識しておくことが重要です。
◎ 導入金融機関はまだ限定的 このサービスは2020年頃からスタートした比較的新しい制度であり、すべての金融機関で導入されているわけではありません。代表的な導入金融機関とサービス名は以下の通りです。
三菱UFJ銀行(予約型代理人-エピソード-)
三井住友銀行(代理人指名手続)
みずほ銀行(みずほの代理人)
りそな銀行(代理人指名サービス)
イオン銀行(代理人届出制度)
各行でサービス内容や手続き、代理人の範囲などが異なるため、利用を検討する際は必ず取引銀行に詳細を確認しましょう。
◎ 制度上の限界とリスク このサービスには、法的な制度である成年後見制度と異なる、以下のような限界やリスクも存在します。
代理人の変更が難しい:契約時に指定した代理人が本人より先に亡くなったり、関係が悪化したりした場合でも、本人の判断能力が低下した後では代理人の変更は原則できません。
監督機能がない:家庭裁判所が選任する後見監督人のような、代理人の活動をチェックする第三者の仕組みがありません。万が一、代理人が不適切な資金の利用をしても、外部から介入・是正することが困難です。
このため、成年後見制度(家庭裁判所が後見人を選任・監督)や、家族信託(契約内容に応じて監督人を設置可能)といった他の制度に比べ、客観的な安全性や透明性の面では課題があるともいえます。誰を代理人に指定するかは慎重に判断し、家族間で取引内容を共有するなどのルール作りが求められます。
【参考コラム】
5. 代理人カードと家族信託・成年後見制度の違い(比較表あり)
高齢者の財産管理には、「銀行の代理人カード」のほかにも、「家族信託」や「成年後見制度(法定後見・任意後見)」といった選択肢があります。それぞれ制度の仕組みや開始時期、費用、継続性に違いがあり、一長一短です。この章では、各制度の特徴を比較表にまとめ、違いや選び方のポイントをわかりやすく解説します。
5-1. 主な財産管理制度の比較表(代理人カード/家族信託/成年後見)
| 比較項目 | 代理人カード(銀行) | 家族信託(民事信託) | 成年後見制度(法定・任意) |
|---|---|---|---|
| 対象財産の範囲 | 指定した銀行の普通預金口座のみ | 信託契約で指定した財産(預金・不動産など) | 本人の全財産(預金・不動産・年金等) |
| 開始時期 | 本人が元気なうちに申請(即日利用可) | 本人が元気なうちに信託契約 | 判断能力が低下した後(申立て後) |
| 認知症発症後の対応 | 原則利用不可(口座凍結)※一部銀行で予約型あり | 対応可能(信託契約に基づき受託者が管理) | 対応可能(後見人が管理) |
| 身上監護(介護契約など) | 不可(預金管理のみ) | 不可(財産管理のみ) | 可能(介護・医療・施設契約など) |
| 法的拘束力 | 銀行内の任意制度(契約による運用) | 信託法に基づく契約 | 公的制度(家庭裁判所による監督) |
| 不正防止・監督体制 | 基本的に無し(家族の信頼前提) | 任意で信託監督人等を置ける | 家庭裁判所が監督(定期報告・帳簿検査など) |
| 費用 | 手数料無料~1,000円程度/維持費なし | 契約書作成・登記等で数十万円~ | 初期費用+専門職後見人報酬(年数十万円) |
| 終了時の対応 | 本人死亡で口座凍結・サービス終了 | 本人死亡または信託契約で定めた時点で終了。財産は指定された人へ承継 | 本人死亡で後見終了。財産は相続手続きへ |
補足:任意後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見」に加えて、本人が元気なうちに契約を結んでおく「任意後見制度」があります。これは、信頼できる人と公正証書で契約を結び、将来、本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所の認可を受けて後見がスタートする制度です。柔軟に内容を決められ、本人が後見人を選べる点が特徴ですが、任意後見監督人(弁護士・司法書士などの専門家)が必ず選任されるため、任意後見監督人の報酬(月額1万円~2万円程度)が必ず発生します。
それぞれの制度には異なる特徴と適した活用場面があります。この章では、代理人カード・家族信託・成年後見制度(法定・任意)の3つについて、それぞれの活用イメージと専門家としてのアドバイスをわかりやすく解説します。
■ 代理人カード
「親が体調を崩した」「急に銀行に行けなくなった」といったときに、家族がすぐに預金を引き出す手段を用意しておきたい場合に適した制度です。銀行窓口で所定の書類を提出するだけで申請でき、即日発行されるケースも多く、費用負担もほとんどありません。
ただし、認知症が進んで名義人の意思確認ができなくなるとカードは使えなくなるため、あくまで一時的な備えとして捉える必要があります。長期的な財産管理や相続を見据えるのであれば、後述する制度との併用が望ましいです。
■ 家族信託
本人が元気なうちに契約できるなら、柔軟性と実効性のバランスに優れた財産管理の方法です。たとえば、預金、不動産、株式などを信託財産とし、その管理・運用・処分を家族(受託者)に任せることができます。認知症になった後も資産を安全に管理し続けることが可能です。
さらに、信託契約の中で死亡後の承継先(例:子どもや孫)を指定できるため、遺言書の代わりとしての役割も果たすことができます。契約時の費用(公正証書作成費用・登記費用など)はかかりますが、家庭裁判所の関与を避け、家族だけで完結できる安心感があります。
【参考コラム】
■ 成年後見制度(法定・任意)
すでに本人の判断能力が低下している場合には、法律に基づいて本人を保護する制度として非常に有効です。家庭裁判所が選任する成年後見人には、法律上の代理権が付与され、預金の引き出しから不動産の売却、介護施設の入所手続きまで、包括的なサポートが可能です。
一方で、申立てに必要な書類や医師の診断書の準備、定期的な家庭裁判所への報告など、事務負担や費用の面でハードルが高い制度でもあります。
実務上は「最終的なセーフティネット」として位置づけ、できれば他の制度で対応できるように事前の準備をしておくことが理想的です。
5-2. まとめ:家族ごとの最適な組み合わせを
どの制度も万能ではありません。大切なのは、家族の状況や資産内容に応じて、制度を組み合わせて備えることです。たとえば、
「当面は代理人カードで対応し、1~2年以内に家族信託へ移行」
「預金は信託、不動産は後見制度で管理」
「財産管理は信託、身上監護は任意後見で備える」
など、複数制度を補完的に使うことで、より実効性のある認知症対策が可能になります。迷った場合は、家族信託や後見に詳しい司法書士などの専門家に相談することで、状況に応じた最適なプランを設計することができます。
6. 実際にあったトラブル事例とその回避策(家族信託の活用)
ここでは、銀行の代理人カードでは対応しきれず、やむを得ず成年後見制度を利用することになったケースを紹介し、その教訓から「本来は家族信託を使って備えるべきだった」という視点で回避策を解説します。認知症リスクが現実となったとき、どのような問題が発生するのか、そしてどうすれば防げたのかを見ていきましょう。
6-1. 事例:認知症により成年後見制度を利用せざるを得なかったケース
Aさん(50代)は、父親(80代)から代理人カードを託され、「何かあったらお願い」と言われていました。父親は元気なうちは預金や定期預金の管理をすべて自分で行っており、Aさんは「いざという時に備えておけば安心」と考え、代理人カードだけを用意していました。
しかし、数年後に父親が認知症を発症し、銀行窓口での手続きの際に銀行員から「意思確認ができない」と判断され、口座が凍結。代理人カードも同時に無効となりました。これにより、Aさんは預金にアクセスできなくなり、介護施設の入居費や医療費を父親の口座から支払うことができない状況に。
司法書士に相談した結果、やむなく成年後見制度の申立てを行うことになりました。煩雑な申立手続きや家庭裁判所の審判などで、成年後見人が決定するまでに約3ヶ月もかかりました。
Aさんは「最初から家族信託など、もっと自由度のある制度を選んでおけばよかった」と後悔しましたが、その時点ではすでに父親の判断能力が失われており、信託契約を結ぶことは不可能な状態でした。
6-2. 家族信託をしておけば避けられた事態
もしAさんが、父親の認知症が進行する前に家族信託契約を結んでいれば、上記のようなトラブルは未然に防げたはずです。
たとえば、父親を委託者兼受益者、Aさんを受託者として、父親名義の預貯金や不動産を信託財産として管理対象に組み入れることができます。信託契約では、「Aさんが父親の医療費や介護費用を信託財産から支払うことができる」と明記しておけば、認知症が進行してからも家庭裁判所の手続きを経ずに柔軟な財産管理が可能になります。
家族信託の最大の特徴は、本人が判断能力を失っても、受託者が信託財産を適切に管理・処分できる点です。また、契約時に死亡後の承継先も定めておけば、遺産分割協議を経ることなく財産をスムーズに相続させることもできます。
このように、家族信託は「認知症リスク」と「相続対策」を同時に備えることができる優れた制度です。
6-3. 本事例の教訓
代理人カードは便利な制度ですが、判断能力の低下=制度の終了という明確な限界があります。成年後見制度は法的な代理権を与える強力な制度ではあるものの、家族にとっては時間・費用・手間の負担が非常に大きく、自由度も限られます。
一方、家族信託は事前に契約することで、本人の意思に沿った柔軟な財産管理ができる上、第三者を介さず家族内で対応を完結できます。
このようなトラブルを避けるためにも、本人に判断能力が残っているうちに信託契約を結ぶことが極めて重要です。早めに司法書士など専門家に相談し、ご家族にとって最適な備えを講じておくことを強くおすすめします。
7. 専門家としての実務経験に基づくアドバイス
これまで、親の財産管理のための様々な制度を見てきました。それぞれに特徴があり、「自分の家族にはどれが合うのだろう?」と悩まれる方も多いでしょう。ここでは、相続や認知症対策を専門とする司法書士としての実務経験を踏まえ、制度選びのポイントや、ご家庭の状況に合わせた最適な対策の考え方をお伝えします。
7-1. 家族会議の重要性
まず、私が一番に強調したいのは「備えは、早ければ早いほど選択肢が広がる」ということです。
認知症への対策は、ご本人様が元気で判断能力がはっきりしているうちにしか行えないものが大半です。例えば、柔軟な財産管理を実現する「家族信託」や、もしもの時の後見人をあらかじめ決めておく「任意後見契約」は、ご本人様の意思に基づいて契約を結ぶため、判断能力が低下した後では利用できません。銀行の代理人カードの発行も同様です。
「うちはまだ大丈夫」と先延ばしにせず、少しでも変化を感じたら、できるだけ早く家族で話し合いの場を持つことをお勧めします。
その際、最も大切なのは親御さん本人の気持ちを尊重することです。いきなり「財産の管理を任せてほしい」と切り出すと、プライドを傷つけられたり、「財産を狙っているのでは?」と不信感を抱かれたりする原因になりかねません。
まずは日頃のコミュニケーションを大切にし、「最近、振り込め詐欺の手口が巧妙で心配だね」「もし入院したら、支払いはどうしようか」といった具体的な話題から、親御さん自身の「もしもの時にどうしたいか」という希望を優しく聞き出すことから始めましょう。親子間で安心して協力できる信頼関係を築くことが、スムーズな対策への第一歩となります。
7-2. 家族構成や資産状況に合わせて対策を考える
どの制度が最適かは、ご家庭の状況によって全く異なります。ここでは、代表的な3つのケースをご紹介します。
ケースA:お子様が一人で、主な資産は預金のみ
【状況】高齢のお母様と、お子様がお一人のご家庭。資産は預金数百万円。
【提案】この場合、相続で揉める可能性は低いため、まずは「代理人カード」を作成し、お子様が日々の入出金をサポートする形でも十分かもしれません。財産規模から考えると、専門家費用のかかる家族信託のメリットは小さいでしょう。将来の認知症に備えるなら、元気なうちに「任意後見契約」をお子様と結んでおき、いざという時に家庭裁判所の手続きを経て後見を開始できるように準備しておく、という組み合わせが考えられます。
ケースB:お子様が複数いて、資産に自宅不動産が含まれる
【状況】お子様が二人以上。資産は自宅不動産と預金2,000万円超。
【提案】お子様が複数いる場合は、将来の相続まで見据えた「家族信託」の活用が有効です。例えば、お母様を「受益者(利益を受ける人)」、長男を「受託者(財産を管理する人)」として自宅と預金を信託します。これにより、長男がお母様の生活費や介護費のために柔軟に財産を管理・処分でき、お母様が亡くなった後には、残った財産を「子どもたちに均等に分ける」といった内容をあらかじめ契約で定めておけます。これにより、お母様の存命中も安心なうえ、円満な相続を実現できます。契約内容に次男も関与し、「受益者代理人(受益者の権利を守る人)」などの役割を担うことで、より公平で透明性の高い運用が可能になります。
ケースC:賃貸不動産や株式など、専門的な管理が求められる資産がある場合
【状況】賃貸不動産や自社株など、継続的な運用・管理が必要な資産をお持ちの方は、判断能力の低下や相続時の混乱を防ぐため、より計画的かつ制度的な備えが重要になります。
【提案】こうしたケースでは、家族信託・任意後見・遺言書を組み合わせるハイブリッドな対策が有効です。それぞれの制度の特性を活かし、「誰が、いつ、どのように管理・承継していくのか」を明確にしておくことで、資産の安全性と承継の円滑さを両立できます。
複雑な資産構成をお持ちの方ほど、制度選択の誤りが将来のトラブルにつながりやすくなります。ご家族の状況やご自身の意思に沿った仕組みを構築するためにも、司法書士など専門家と連携しながら、早めに対策を進めることが大切です。
このように、ご家庭の事情に合わせて各制度を柔軟に組み合わせることが重要です。一度に全てを決めるのが難しい場合は、まず代理人カードで当面の生活を支えつつ、並行して家族信託や後見の準備を進めるという段階的なアプローチも有効です。
7-3. 専門家に相談するときのコツ
司法書士や弁護士などの専門家に相談する際は、事前にご家族の意向と大まかな財産状況を整理しておくと、話が非常にスムーズに進みます。
「誰に財産の管理を任せたいか」「将来の遺産分割について、どのような希望があるか」「後見人や受託者(財産を託される人)に適任な家族はいるか」といった点をご家族で話し合ったうえで専門家に伝えると、より具体的で的確な提案を受けやすくなります。
そして、相談は早ければ早いほど良い、ということをどうか覚えておいてください。認知症が進行してしまうと、法的に有効な契約を結べなくなり、打てる手が限られてしまいます。私たちの事務所にも、「もっと早くご相談いただけていれば、ご家族の希望に沿った家族信託で対応できたのに…」と、悔しい思いをするケースが後を絶ちません。初回相談を無料で行っている専門家も多いので、少しでも気になった時点で、まずは話を聞いてみることを強くお勧めします。
最後に、どんな制度を利用するにせよ、ご家族の協力体制が何よりも不可欠です。特に家族信託は、家族間の合意なくしては始まりません。ご兄弟姉妹がいる場合は、全員にとって納得感のある公平な計画を立てることが「争族」を避ける鍵となります。
制度は、あくまでご家族の未来を守るための「道具」にすぎません。最も大切なのは、ご本人とご家族が、この先の人生を安心して迎えられること。ぜひ、皆様のご家庭にとって最善の方法を、私たち専門家と一緒探していきましょう。
【参考コラム】
8. まとめ:代理人カードをきっかけに、将来の備えを考えよう
銀行の代理人カードは、高齢の親の預金管理を支える有効なツールです。本人が銀行に行けなくなった場合でも、家族がATMで入出金できる手軽さと安心感は大きな魅力です。
ただし、代理人カードはあくまで本人に判断能力がある間に限定され、認知症が進行すれば使えなくなる点には注意が必要です。たとえ予約型代理人サービスを利用しても、対応できるのは銀行取引に限られます。預金以外の資産や生活全般の管理には、家族信託や成年後見制度の活用が欠かせません。
大切なのは、親の状況や家族の体制に応じて、複数の制度を柔軟に組み合わせることです。たとえば、日常の出し入れは代理人カード、資産全体の管理は家族信託、将来に備えて任意後見契約を結ぶといった設計が考えられます。こうした対策は、早めに家族で話し合い、司法書士などの専門家とともに進めることで、現実的かつ効果的な形に整えることができます。
司法書士法人ミラシアでは、代理人カードの活用方法から、信託や後見制度を組み合わせた総合的なプランニングまで幅広くサポートしています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。大切なご家族の安心のために、早めの一歩をおすすめします。

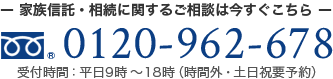
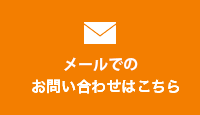
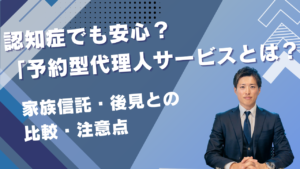
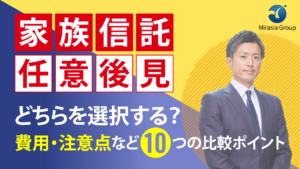
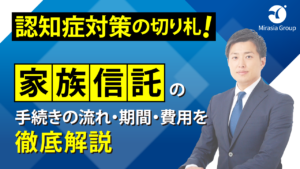
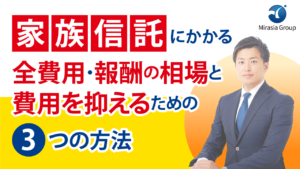
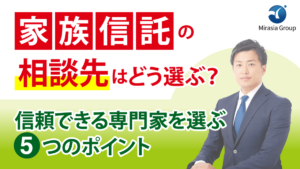
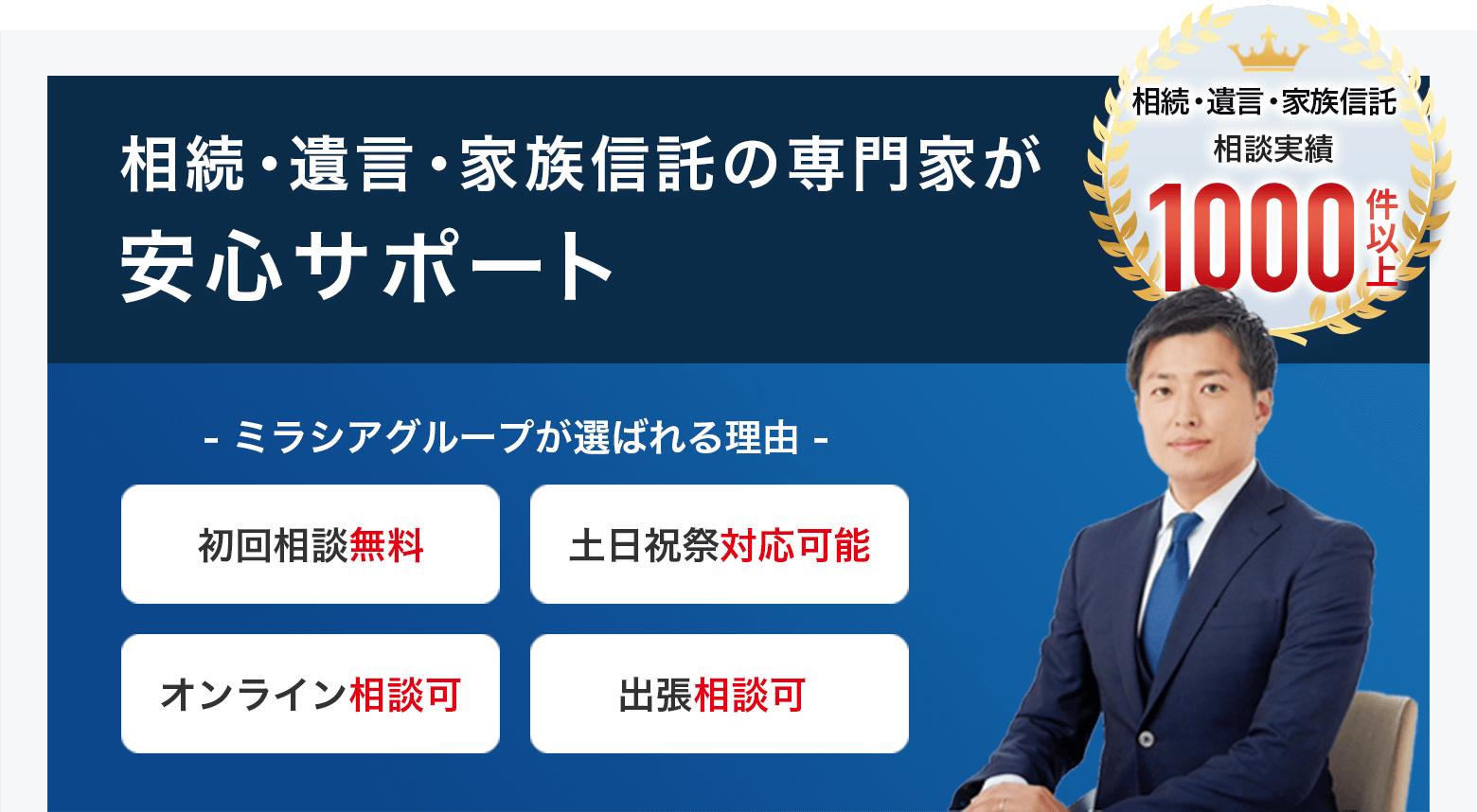
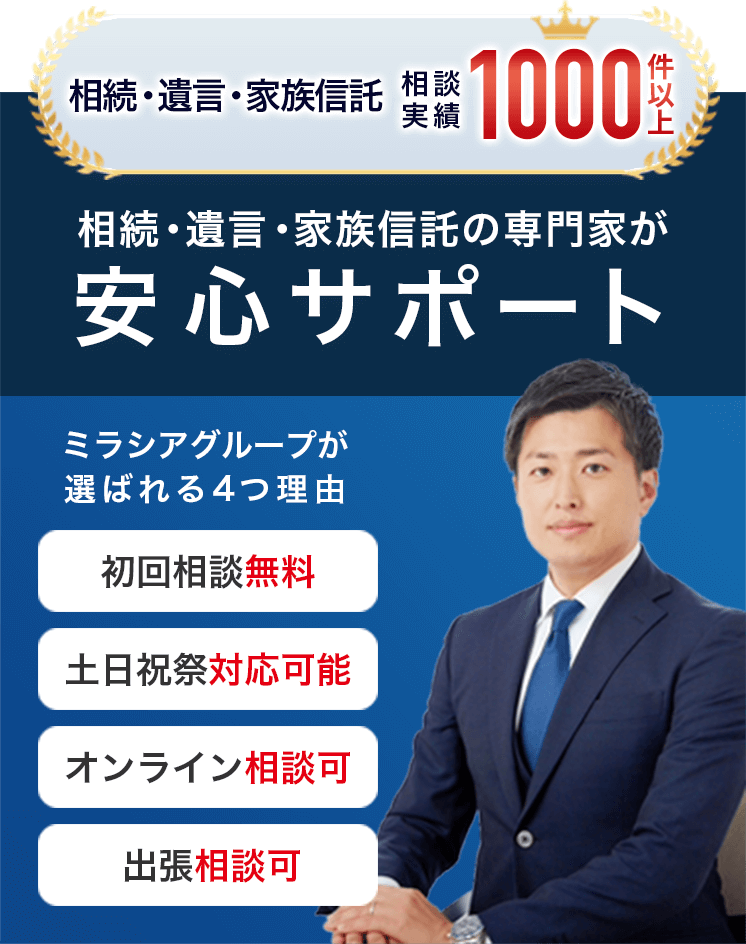


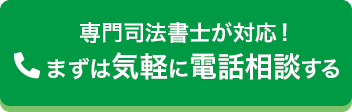
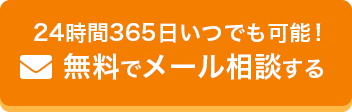
コメント