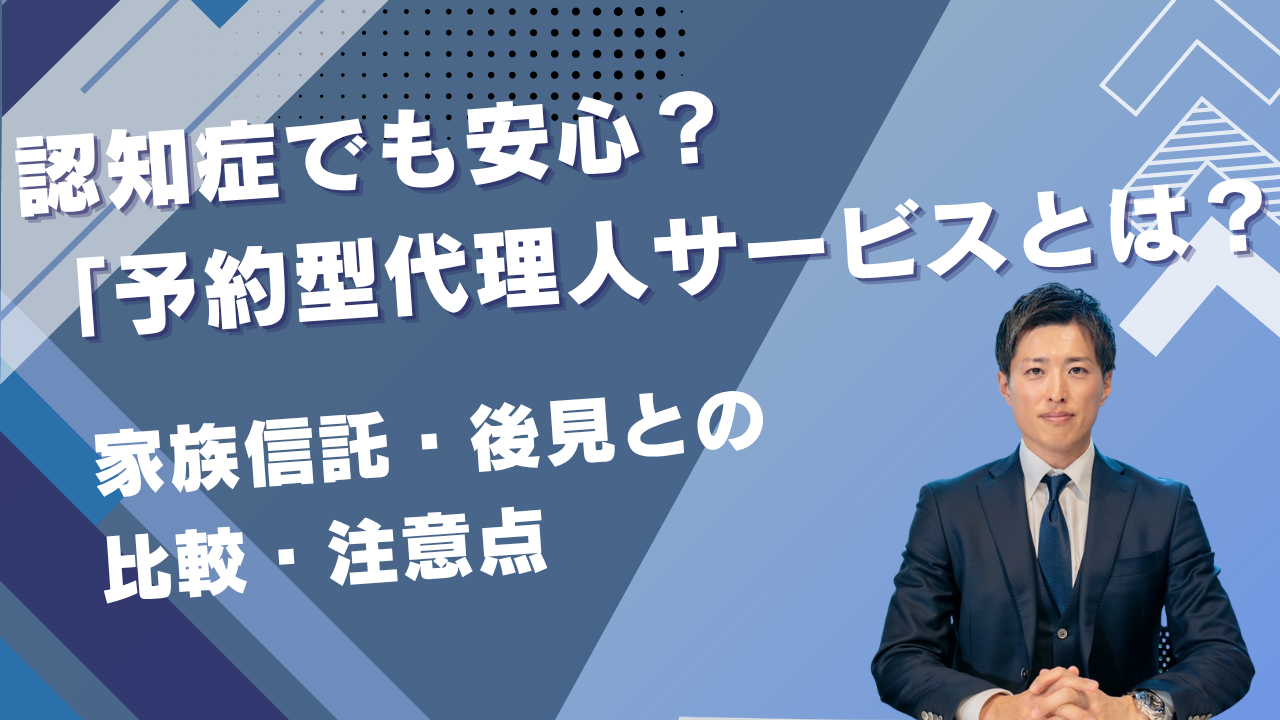
目次
1. 予約型代理人サービスとは
もしも高齢の親が認知症になってしまったら──
そんなとき、病院や介護施設の費用を払うために、親名義の預金を引き出そうとしても「もうご本人の意思確認ができないため、お手続きできません」と銀行で断られるケースが少なくありません。実際に、認知症などで判断能力が低下すると、たとえ実の子どもや配偶者であっても、勝手に預金を引き出すことはできなくなります。銀行はご本人の資産を守るため、口座の利用を制限する措置、いわゆる「口座凍結」を行うのです。
一度口座が凍結されてしまうと、ATMでの引き出しも、定期預金の解約も、窓口での手続きもストップします。介護費用や突然の入院費用などが親の口座からは支払えなくなる可能性があります。
このような事態に備える方法として、以前から成年後見制度(法定後見・任意後見)がありました。しかし、後見制度を利用するには家庭裁判所での手続きが必要で、申立書類の準備や医師の診断、場合によっては数か月の時間を要するうえ、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われることになります。「手続きが煩雑で、柔軟な対応が難しい」と感じる方も多く、実際には制度の利用に二の足を踏むご家族も少なくありません。
そんな中で近年注目されているのが、銀行が提供する「予約型代理人」サービスです。これは、本人がまだ元気なうちに、将来もし認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ「この人に口座の手続きを任せたい」と代理人を登録しておく制度です。いざという時には、事前に登録した代理人が、本人に代わって預金の払い戻しや振込、各種手続きができるようになります。
「もしもの時に口座が使えない」という事態を未然に防ぐ、有効な仕組みとして注目が高まっているこの制度について、本稿では認知症対策専門の司法書士が、制度の仕組み、メリット・デメリット、成年後見や家族信託との違い、実際の活用事例などをわかりやすく解説します。
1-1. サービスの概要
予約型代理人サービスとは、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来自分の代わりに銀行での取引を任せたい家族(代理人)を、あらかじめ銀行に届け出ておく制度です。代理人として登録できるのは、通常は配偶者や二親等以内の親族(子ども・兄弟姉妹・孫など)で、銀行によっては事実婚のパートナーなども認められる場合があります。
将来、本人の認知機能や判断能力が低下し、自ら銀行取引を行うことが難しくなった際には、代理人が医師の診断書など所定の書類を銀行に提出することで、本人に代わって預金の出し入れや各種手続きを行えるようになります。
ただし、代理人が実際に取引を始めるまでの間は、本人自身が通常通り口座を管理することになります。この制度はあくまで「もしも」のときに備えて事前に代理人を“予約”しておく仕組みであり、本人の判断能力が保たれている限りは、従来通りご本人が自由に口座を利用できます。
1-2. どんな取引ができる?
代理人ができる手続きの範囲は銀行によって若干異なりますが、一般的には以下のような日常的な銀行業務が含まれます。
預金の引き出しや振込
定期預金の解約
公共料金などの支払い
通帳やキャッシュカードの再発行
住所変更の手続き
残高証明書の取得
また、証券口座を開設している場合は、有価証券の売却や送金などの手続きも含まれることがあります。つまり、介護費用や医療費の支払い、生活費の管理など、日常の資金管理に必要な大半のことは、代理人によって行うことが可能です。
ただし、注意が必要なのは、この制度で代理人が対応できるのは「登録した銀行の口座に関する取引のみ」であるという点です。他の金融機関の口座や、不動産の売買・賃貸契約など、銀行以外の手続きには対応していません。
また、代理人が取引を始めるには、銀行所定の形式で作成された医師の診断書の提出が必要です。この診断書で、本人の判断能力の低下が明確に証明された場合にのみ、代理人が動ける仕組みです。
つまり、「最近もの忘れが増えてきたから、念のため取引を任せたい」といった軽度の心配段階では代理権は発動せず、一定以上に認知機能の低下が進行していなければ、代理人として手続きを行うことはできません。
1-3. 利用できる金融機関
この予約型代理人制度は、全国銀行協会が2021年にガイドラインを公表したことをきっかけに、全国の金融機関で導入が進みました。現在は以下のような銀行でサービスが提供されています。
三菱UFJ銀行(「予約型代理人サービス」)
三井住友銀行(「代理人指名手続」)
みずほ銀行(「代理人予約サービス」)
イオン銀行
- 大和証券 など
これに加えて、一部の地方銀行や信用金庫でも対応を開始しているところがあります。例えばみずほ銀行では、代理人が医師の診断書を提出することで、預金の引き出し・解約、投資商品の売却、住所変更などの手続きを無料で行うことができます(診断書の取得費用は自己負担)。サービスの名称は銀行によって異なりますが、いずれも共通して「認知症等による口座凍結に備えるための事前対策」という目的で提供されています。
ただし、申し込みは銀行ごとに個別に行う必要があるため、たとえば三菱UFJ銀行で代理人登録しても、他行の口座にはその効力は及びません。複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの銀行で個別に申し込みを行う必要があります。
申し込みの際は、本人と代理人が一緒に銀行窓口を訪れて手続きを行う必要があり、所定の申込書を提出します。郵送やインターネットでの受付には対応していない銀行がほとんどです。
一度登録すれば定期的な更新は不要で、継続的に有効な登録となりますが、重要な注意点として、本人の判断能力が低下した後では新たな代理人登録はできません。したがって、「まだ元気なうち」に備えておくことが何よりも重要です。
2. 予約型代理人のメリット・デメリット
では、この予約型代理人サービスには具体的にどんなメリットがあり、どんな点に注意すべきでしょうか?成年後見制度など他の方法と比べた長所・短所を踏まえ、専門家の視点から解説します。他サイトで言及されている一般的な事項だけでなく、実務上感じるポイントや実例も交えてお伝えします。
2-1. 予約型代理人サービスのメリット
予約型代理人サービスには、次のようなメリットがあります。
1. 手続きが簡単でスピーディー
成年後見制度のように家庭裁判所に申し立てる必要はなく、銀行で所定の届出を行うだけで手続きが完了します。将来、本人の判断能力が低下した際には、代理人が診断書を提出することで、速やかに代理取引が開始できるため、急な資金手当てにも対応しやすい制度です。
2. 費用負担が非常に少ない
制度の利用自体に費用はかからず、契約書の作成や専門職への依頼も不要です。かかるのは、発動時に必要となる医師の診断書作成費用(数千円~1万円程度)程度で済みます。成年後見制度や家族信託に比べると、低コストで対策を行うことができます。
3. 銀行内で手続きが完結し、家族だけで進められる
すべての手続きが銀行窓口で完結するため、煩雑な法的書類の作成や家庭裁判所とのやりとりは不要です。必要書類も、本人・代理人の本人確認書類や印鑑証明書など、一般的に準備しやすいものに限られており、多くの場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずとも家族だけで対応できます。
4. 判断能力がある間は、本人が自由に管理できる
代理人が実際に代理人として権限を持つのは、本人の判断能力が低下した後なので、「元気なうちは自分で管理したい」という方に向いている
5. 口座凍結を未然に防げる
この制度の最大のメリットは、本人の認知症進行後も、事前登録された代理人が銀行取引を行えるため、口座凍結によって生活費や介護費、入居一時金などの支払いに困るリスクを防げることです。大切な預貯金を「いざというとき」に使えないまま眠らせてしまう事態を回避できます。
2-2. デメリット・注意点
一方、便利な制度ではありますが、利用にあたっては次のような制限や注意点があります。
1. 指定できる代理人に制限がある
代理人として登録できるのは、原則として配偶者または二親等以内の親族に限られます。一部の銀行では事実婚パートナーも認められる場合がありますが、公的証明が求められます。また、申込時には銀行による審査が行われ、事情によっては代理人として認められないケースもあるため、誰でも登録できるわけではありません。
2. 利用できる範囲は特定の銀行に限られる
この制度は各銀行が独自に運用しているサービスのため、登録した銀行でしか有効ではありません。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行で個別に申し込む必要があります。また、すべての金融機関が対応しているわけではなく、地方銀行やゆうちょ銀行では導入されていないこともあるため、希望する口座で利用できないケースもあります。
3. 管理できる資産の範囲が限定的
代理人が手続きできるのは、登録した銀行の口座に限られます。たとえば、不動産の売却、他の金融機関の口座解約、介護施設との契約手続きなど、銀行外の取引には対応していません。資産全体を包括的に管理したい場合は、家族信託や成年後見制度など、別の手段を組み合わせる必要があります。
4. 発動には医師の診断書が必須
代理人が実際に動けるのは、銀行所定の形式で作成された診断書により、本人の判断能力が明確に低下していると認められたときに限られます。軽度の認知症や、物忘れが気になる段階では制度を発動できません。主治医が診断書の作成に協力してくれない場合や、本人が受診を拒否する場合など、発動のタイミングを逃す可能性もあります。
5. 代理人の不正リスクに対する監督がない
この制度には家庭裁判所などの外部監督機関が存在せず、代理人の行動は実質的にチェックされません。そのため、悪意ある代理人が不正に預金を引き出すリスクがあります。信頼できる人を選ぶことが大前提であり、家族間での情報共有や通帳の管理ルールなど、透明性を保つための工夫が不可欠です。
6. 発動後の取引には代理人の「来店」が必須
代理人が実際に銀行口座からお金を引き出したり、振込・解約などの取引を行う場合は、銀行窓口へ直接来店する必要があります。ATMやネットバンキングによる取引は認められていないケースが多く、遠方に住んでいるご家族や仕事で平日昼間に動けない方にとっては大きな負担になる場合があります。
7. 本人のキャッシュカードやネットバンキングは利用停止に
予約型代理人サービスが発動すると、本人のキャッシュカードやネットバンキングは原則として利用停止となります。これは、判断能力の低下が確認された状態での誤操作や、第三者による不正利用を防ぐために、銀行が本人の口座への直接アクセスを遮断する措置です。
つまり、本人が一部でも判断能力を保っていたとしても、銀行は安全性を最優先に、本人の取引手段が停止します。そのため、施設入所中の本人が「自分で少しでも引き出したい」と思っても、それができない状況になります。
なお、この制限は「代理人カード」とは明確に異なる運用であり、日常的な利便性を目的とした制度ではないことに留意が必要です。
3. 「代理人カード」との違い
3-1. 代理人カードとは
予約型代理人サービスとよく混同されるものに、「代理人カード」という制度があります。銀行の代理人カードとは、口座名義人本人に代わって、指定された代理人がATMでの入出金などの取引を行えるようにするためのキャッシュカードです。主に、口座名義人が高齢や病気、入院などで銀行窓口やATMに行くことが困難な場合に、家族などが生活費や医療費を引き出すために利用されます。
3-2. 代理人カードで「できること」「できないこと」
代理人カードで利用できる機能は、金融機関によって多少異なりますが、一般的に以下の範囲に限定されています。
ポイントは、あくまで日常的な入出金を代行するためのカードであり、口座の根本に関わるような重要な取引は行えないという点です。
代理人カードの詳細は下記をご覧ください。
【参考コラム】
3-3. 予約型代理人サービスと代理人カードの比較
それでは、以下に両者の違いを整理します:
| 比較項目 | 予約型代理人サービス(判断能力低下後) | 代理人カード(判断能力あり) |
|---|---|---|
| 利用開始の条件 | 医師の診断書による「判断能力低下」の証明 | 本人の申込・同意のみで利用開始可能 |
| 主な取引場所 | 銀行の窓口 | ATM(ネットバンキングは不可) |
| 本人のカード・ネットバンキング | 利用停止となる(本人が操作できない状態) | そのまま利用可能 |
| 目的 | 認知症時の口座凍結対策、資金の緊急対応 | 買い物や公共料金の支払いなど、日常生活の補助 |
| 監視体制・安全性の高さ | 窓口対応により比較的高い | ATM利用であり、家族間の信頼が前提 |
このように、「予約型代理人サービス」は便利な反面、代理人が毎回銀行窓口へ出向く必要があるという運用上の負担が伴います。離れて暮らす家族や、仕事で平日動きづらい方にとっては、制度発動後の実務運用が想像以上に大変となるケースもあります。事前に家族でよく話し合い、「誰が・どのように動けるか」を確認しておくことが重要です。
4 事例:予約型代理人で口座凍結を防げたケース
最後に、筆者が相談を受けたケースをもとに、予約型代理人の有用性を具体的にイメージできる事例をご紹介します。
〈事例〉 80代のAさんは自宅で療養中で、妻Bさんと二人暮らし。Aさん名義の預金口座から毎月の年金が支給され、その口座から生活費や医療費を支出していました。数年前、Aさんは万一に備えて銀行で妻Bさんを予約型代理人として届け出ておきました。やがてAさんの認知症が進行し意思疎通が難しくなったため、妻Bさんは主治医に相談のうえ銀行所定の診断書を入手して提出しました。すると銀行は速やかにBさんからの預金引き出しや振込手続きを受け付けてくれるようになり、介護サービス費用や施設の入居一時金も滞りなく支払うことができました。家庭裁判所で後見人を選任する必要もなく、預金残高の範囲で無理なく夫の介護費用を工面できたのです。Bさんは「予約型代理人の手続きをしていなかったら、一時は数百万円の入居金を準備するのに苦労していた。後見人を立てるとなれば時間も費用もかかった思うので、本当に助かった」と安堵しています。
ちなみにAさんのご近所に住むCさん(75歳男性)は同じく認知症を発症しましたが、事前の備えがなく口座が凍結されてしまったため、ご家族がやむなく成年後見を申し立てました。後見開始までに約3か月を要し、その間介護施設への支払いに家族が立て替える負担も生じました。「もっと早く予約型代理人サービスを知っていれば…」とCさんのご家族はこぼしていました。この対照的な例からも、判断能力があるうちに備えを講じておくことの重要性がお分かりいただけるでしょう。
5. 成年後見制度との違い
予約型代理人サービス(銀行の事前代理人制度)は、成年後見制度に比べて手軽に利用できるメリットがあります。しかし両者の違いを正しく理解し、それぞれ「何ができて何ができないか」を把握しておくことが大切です。必要に応じて両制度を使い分けられるよう、以下に主要なポイントを整理して解説します(法定後見を念頭に置き、必要に応じて任意後見契約とも比較します)。
5-1. 手続き・開始までの違い
予約型代理人サービスの場合: 本人が元気なうちに銀行で代理人予約の申込を行い、事前に代理人との契約関係を結んでおきます。将来、本人の判断能力が低下した際には、銀行所定の医師の診断書を提出することで代理権が発動します。家庭裁判所の審判などの手続きは不要で、開始までの期間も短く、診断書提出から代理開始まで数日~1週間程度で済みます。
成年後見制度(法定後見)の場合: 本人の判断能力が低下した後、親族等が家庭裁判所へ後見開始の申立てを行い、調査・審問を経て裁判所が後見人を選任します。申立てから審判確定までは一般的に数か月程度かかります。なお、任意後見契約という方法では本人が元気なうちに公正証書で後見人候補と契約を結べますが、実際に契約内容を発動する際には家庭裁判所で後見監督人を選任し契約内容の確認を受ける必要があるため、結局のところ完全に利用できるようになるまで時間と手間がかかる点は共通しています。
5-2. 代理人(後見人)の選び方の違い
予約型代理人サービスの場合: 本人が自分で代理人を指名できます。原則として二親等内の親族(配偶者・子・兄弟姉妹・孫・祖父母など)から選ぶ必要があり、信頼できる家族に任せられる点で安心感があります。ただし、銀行の判断によっては、指定した代理人では申込を受け付けてもらえない場合もあるようです(例えば不正の恐れがあるケースなど、銀行側で不適格と判断される場合)。
成年後見制度(法定後見)の場合: 家庭裁判所が後見人を選任します。親族が後見人に選ばれるケースもありますが、裁判所の判断で司法書士や弁護士などの専門職の第三者が選ばれることもあります。特に本人の資産規模が大きい場合や親族間で利害対立・争いがある場合には、親族以外の専門職後見人が付く傾向があります。また、任意後見契約の場合、本人が後見人候補者を自由に指名できますが、最終的な任意後見監督人は裁判所が指名してチェックする仕組みです。いずれにせよ「誰が財産を管理するか」という点で、予約型代理人は家族主体で決められるのに対し、成年後見では第三者が関与してくる可能性があるという違いがあります。
5-3. 権限の範囲の違い
この点が両者の最大の相違点です。
予約型代理人サービスの場合: 代理人に与えられる権限は文字通り「登録した銀行口座の取引」に限定されます。例えば三菱UFJ銀行でこのサービスを利用した場合、その銀行内の預金や有価証券の管理(払い戻し・解約・振替など)のみ代理人が行えます。しかし、それ以外の財産には一切関与できません。他の銀行の口座や自宅の現金、有価証券、本人名義の不動産の処分などについては代理権がなく、一切手を出せない仕組みです。
成年後見制度(法定後見)の場合: 後見人の権限は法律上非常に広範囲で、本人の財産管理全般を代理できます。預貯金の管理・解約はもちろん、不動産を売却して介護費用に充てることや生命保険の解約なども後見人の職務に含まれます。一部、身上監護的な行為(介護サービス契約の締結や施設入所の手続き等)も法定後見人の権限に含まれ、本人の日常生活に関わる契約を代理することも可能です。ただし、後見人が居住用不動産売却など重要な行為を行う際には家庭裁判所の許可が必要です。
5-4. 費用の違い
予約型代理人サービスの場合: 基本的に費用負担なく利用できます(医師の診断書作成料程度を除く)。銀行での申し込み手数料や代理人カード発行料などは、現時点では設定されていないのが通常です、銀行によっては将来的に手数料が導入される可能性もありますが、少なくとも現状は無料で利用できるケースがほとんどです。
成年後見制度の場合: 法定後見の申立て時には、収入印紙代・郵便切手代など数千円~1万円程度の実費がかかります。場合によっては鑑定費用(数万円)が発生することもあります。さらに後見が開始すると、選ばれた後見人(専門職が就任した場合)や任意後見契約で選任される後見監督人への報酬が毎年発生します。報酬額は本人の資産や収支状況にもよりますが、一般的なケースで年間20~60万円程度とされ、これが本人の財産から継続的に支払われます。経済的負担という面では無視できない大きなコストです。また、任意後見契約を公正証書で結ぶ際には、公証役場での手数料(約1~2万円)も必要になります。このように経済的コストの面では、予約型代理人サービスが圧倒的に有利と言えるでしょう。
5-5. 外部の監督体制と安心感の違い
予約型代理人サービスの場合: 銀行のサービスであり、家庭裁判所など第三者の継続的な監督は一切ありません。代理人の行為は基本的に誰からもチェックされないため、良くも悪くも家族の裁量に委ねられる仕組みです。不正の恐れが全くのゼロとは言えないものの、その反面、裁判所への定期報告義務などがないため事務的負担がなく、柔軟かつ迅速に資金を動かせる利点もあります。
成年後見制度の場合: 法定後見では家庭裁判所が常に後見人の業務を監督します。少なくとも年1回は後見人に対して収支報告書類の提出が課され、不審な点があれば家庭裁判所が調査や場合によっては後見人の解任を行います。任意後見の場合も後見監督人(弁護士等)が就任してチェックする体制になっています。このように第三者の目によるガバナンス(統制)が利いている点は安心材料ですが、その分、家族にとっても事務処理の手間がかかるデメリットがあります。また後見人は家庭裁判所の許可なしに勝手なことはできないため、緊急時の迅速な対応という点では機動力が劣る場面もあります。つまり「手軽さ」と「安心感」のトレードオフ(どちらかを取れば一方が犠牲になる関係)が両制度にはあると言えるでしょう。
以上のように、予約型代理人サービスは銀行口座の管理に特化した簡易な仕組みであり、成年後見制度は本人の財産全般を保護する包括的な制度です。それぞれに長所と短所があるため、ケースに応じて使い分けることが重要です。
例えば「預貯金の管理だけを家族に任せたい」「できるだけ裁判所の世話になりたくない」という場合には、予約型代理人サービスが有効でしょう。一方、不動産を売却して介護費用に充てる必要がある場合や、身寄りがなく専門職に財産管理を依頼したい場合などには、成年後見制度(法定後見)の利用を検討すべきです。また、すでに認知症が進行しているケースでは予約型代理人サービスの新規登録はできません。その場合は迷わず成年後見制度など別の手段に切り替える必要があります。
いずれの制度を利用するにせよ、本人や家族の状況・希望に合わせて最適な方法を選択することが大切です。両者の違いを正しく理解した上で、早めに備えを検討しておくと安心でしょう。
6. 家族信託との違い
では次に、近年注目されている家族信託(民事信託)と予約型代理人の違いを見てみましょう。家族信託とは、本人(委託者)の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、管理・運用や将来の承継方法まで柔軟に定めておく制度です。認知症対策としては、財産を元気なうちに信託に移しておくことで、後に本人が判断能力を失っても受託者である家族が財産を凍結なく管理し続けられるという利点があります。一見すると予約型代理人と目的が似ていますが、仕組みや効果が大きく異なるため注意が必要です。
【参考コラム】
【参考動画】
6-1. 手続き・開始までの違い
予約型代理人サービスの場合: 本人が元気なうちに銀行で代理人予約の申込を行い、事前に代理人との契約関係を結んでおきます。将来、本人の判断能力が低下した際には、銀行所定の医師の診断書を提出することで代理権が発動します。家庭裁判所の審判などの手続きは不要で、開始までの期間も短く、診断書提出から代理開始まで数日~1週間程度で済みます。
家族信託の場合: 通常、公証役場で公正証書による信託契約書を作成し、信託する財産(不動産なら登記、銀行預金なら信託口口座の開設など)を受託者名義へ移す必要があります。専門家への依頼費用や登記費用など、初期コストも発生します。
【参考コラム】
6-2. 管理できる財産の違い
予約型代理人サービスの場合: 対象は登録した銀行口座の預貯金等に限定されます。その他の資産(他行口座、不動産、株式など)には一切関与できません。
家族信託の場合: 現預金、不動産、有価証券など、契約で定めたさまざまな資産を一括で信託財産として管理することが可能です。
【参考コラム】
6-3. 効力の発動・運用の違い
予約型代理人サービスの場合: 判断能力が低下したことを医師の診断書で証明し、初めて代理権が発動します。それまでは本人が口座を自由に管理します。
家族信託の場合: 契約締結と同時に信託の効力が発生し、以後は受託者が財産を管理します。本人の判断能力の有無にかかわらず、受託者が契約に基づいて運用できます。
6-4. 費用の違い
予約型代理人サービスの場合: 基本的に無料で利用できます。かかる費用は診断書の取得費用程度です。
家族信託の場合: 公証役場の手数料、専門家報酬、不動産の登記費用など、数十万円単位の初期費用が発生します。
【参考コラム】
6-5. 本人死亡時の取り扱い
予約型代理人サービスの場合: 本人が亡くなると代理権は消滅し、口座は凍結されます。その後は通常の相続手続きに移行します。
家族信託の場合: 信託契約で本人死亡後の財産承継先を指定することができるため、遺言書と同様の機能を果たします。
6-6. 管理主体と監督体制の違い
予約型代理人サービスの場合: 銀行への届出に基づく私的な仕組みであり、裁判所など外部の監督機関はありません。代理人の管理行為は基本的に家族内で完結します。
家族信託の場合: 信託監督人や受益者代理人など、契約によって一定の監視体制を設けることはできますが、基本的に裁判所の関与はありません。受託者には法的な忠実義務や善管注意義務が課されており、不正があれば損害賠償請求等で追及されることもありますが、日常的なチェック機能はありません。
予約型代理人サービスと家族信託は、いずれも認知症による財産凍結を防ぐための有効な制度ですが、その仕組みや対象範囲には明確な違いがあります。手軽さと導入コストの低さを重視するなら予約型代理人サービスが適しています。一方、不動産や複数の資産を包括的に管理し、死亡後の承継計画まで含めて設計したい場合には、家族信託が効果的です。
たとえば、自宅不動産も含めて将来の相続まで見据えた対策をしたいのであれば、家族信託を活用することで、預金だけでなく不動産も凍結を防ぎ、資産承継の意思を契約で明確にしておくことができます。
その反面、家族信託は設計や手続きに時間と費用がかかるため、動かす財産が自宅と数百万円程度の預金であれば、予約型代理人サービスに加えて、他行口座を整理したり、遺言書を用意したりすることで、現実的かつ十分な対策となるケースも少なくありません。
大切なのは、ご家族の状況や財産の内容を踏まえて、目的に応じた制度を柔軟に組み合わせていくことです。一つの方法に固執せず、信頼できる専門家と相談しながら、最適な形で将来への備えを進めることをおすすめします。
まとめ
「予約型代理人」サービスは、認知症による預金口座の凍結に備えるための、画期的かつ手軽な制度です。家庭裁判所を介さず、家族だけで完結できるという点は、実務を担う司法書士の視点から見ても非常に実用的であり、今後ますます活用が広がっていくことが期待されます。
特に、成年後見制度には抵抗があるものの、「何も対策しないのは不安」というご家庭にとっては、有力な選択肢となるはずです。
ただし、予約型代理人サービスだけですべてをカバーできるわけではないことにも注意が必要です。たとえば、銀行口座以外の財産(不動産・他行預金・証券口座など)の管理や、介護施設の入所契約などの療養看護の支援には対応していません。また、すべての銀行でこのサービスが導入されているわけではないため、対象金融機関の確認も必須です。
また、この制度の大きな前提として「本人の判断能力があるうちにしか利用できない」という点があります。認知症が進行し、意思能力が不十分になってからでは、制度の利用はできません。「そのうちに」と先送りにしてしまうと、制度が使えないまま判断能力が低下してしまう恐れもあります。
だからこそ、今このタイミングで備えを検討することが何よりも重要です。まずは、ご自身やご両親の預金口座の管理状況を確認し、現在利用している銀行で予約型代理人サービスが利用可能かをチェックしてみてください。
そして、「わが家ではどの制度を使うべき?」「家族信託や後見制度とどう組み合わせればいい?」といった疑問や不安がある方は、ぜひ司法書士法人ミラシアの初回無料相談をご活用ください。相続・認知症対策を専門とする司法書士が、ご家族の状況や財産の内容を丁寧にお伺いし、最適な対策プランをご提案いたします。
ご家族の安心と未来のために、できることから一歩ずつ備えていきましょう。備えあれば憂いなしです。

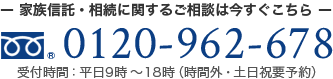
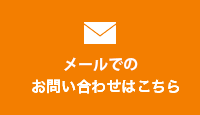
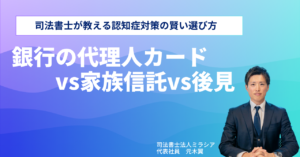
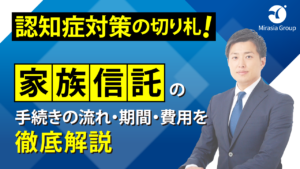
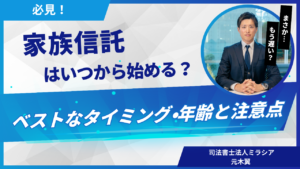
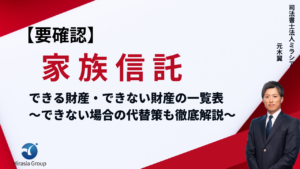
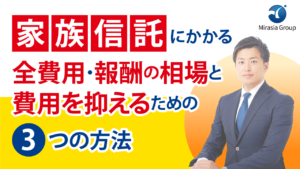
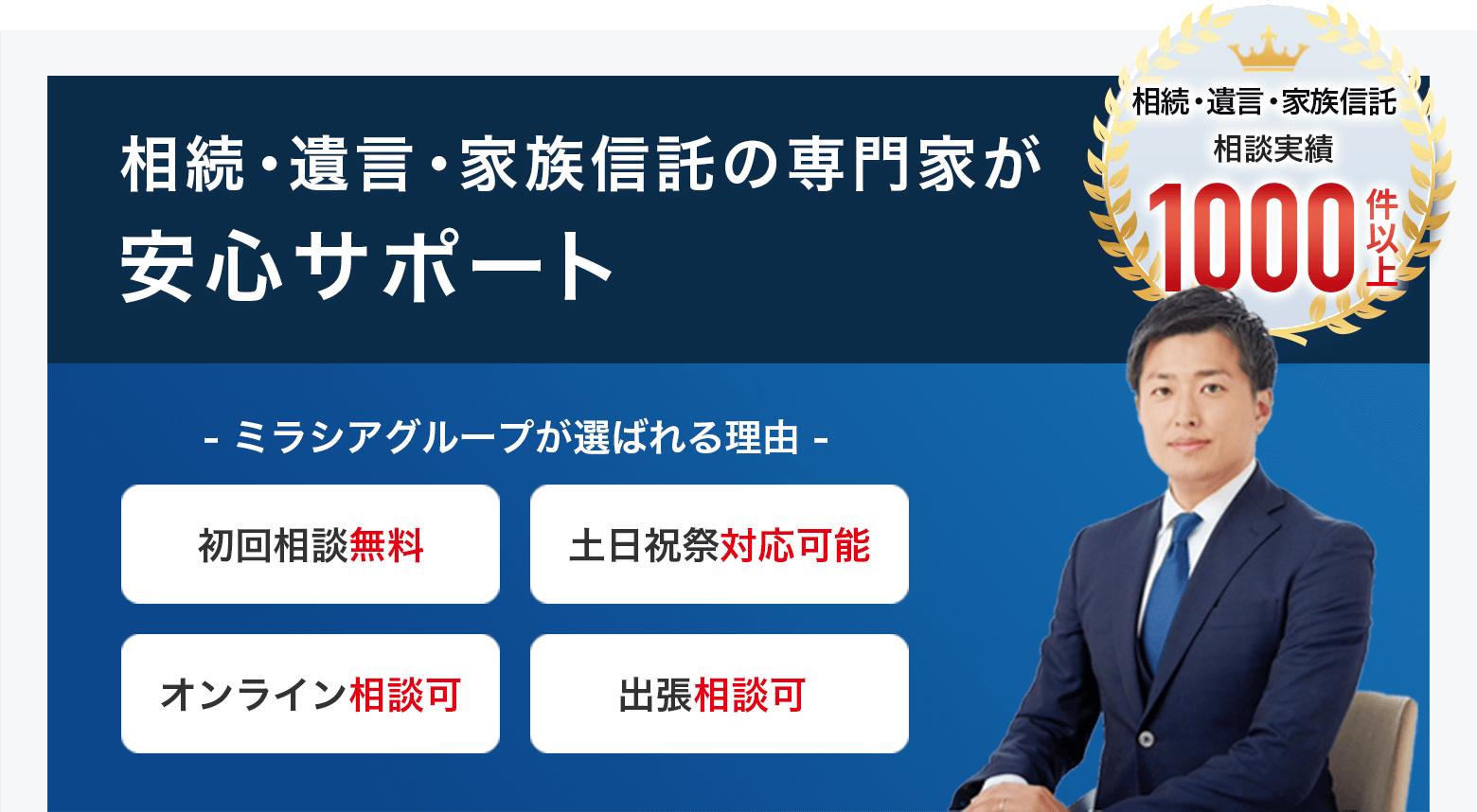
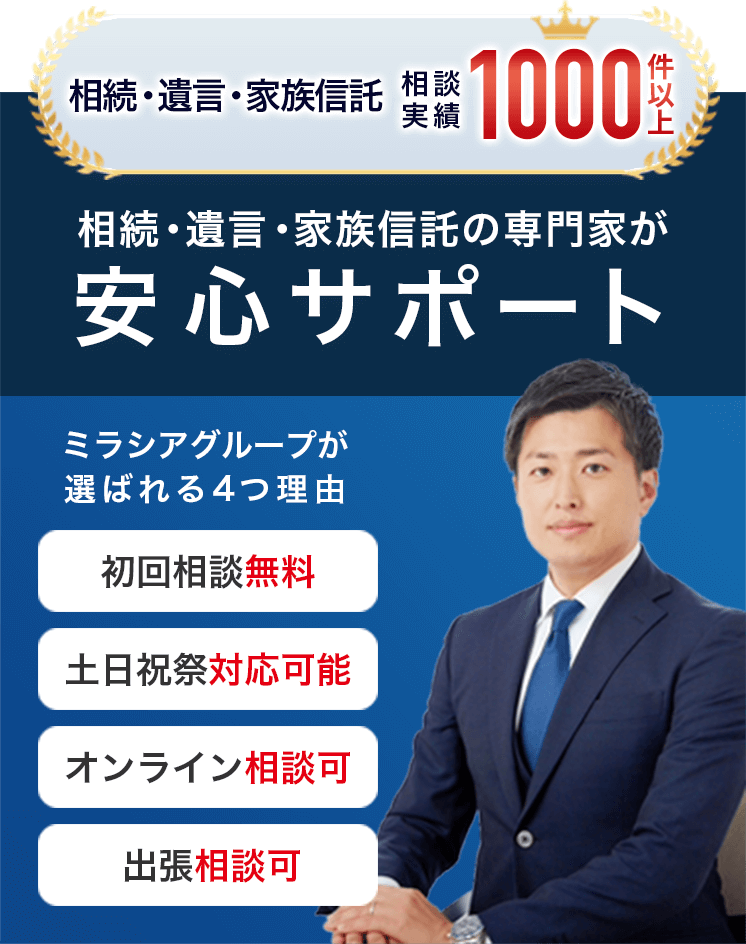


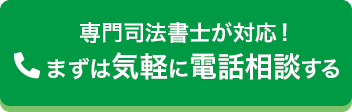
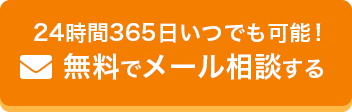
コメント